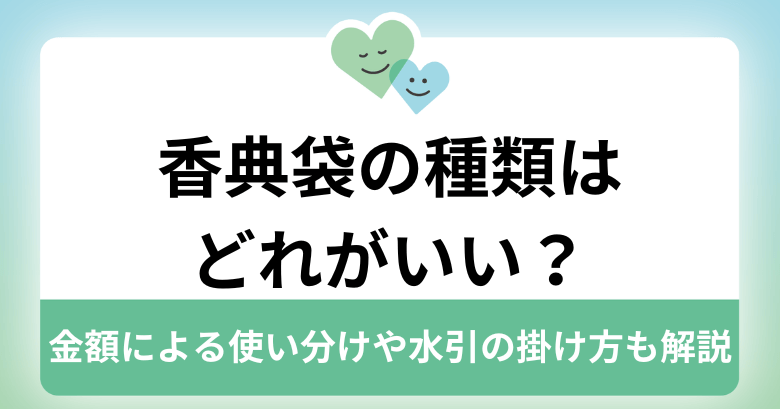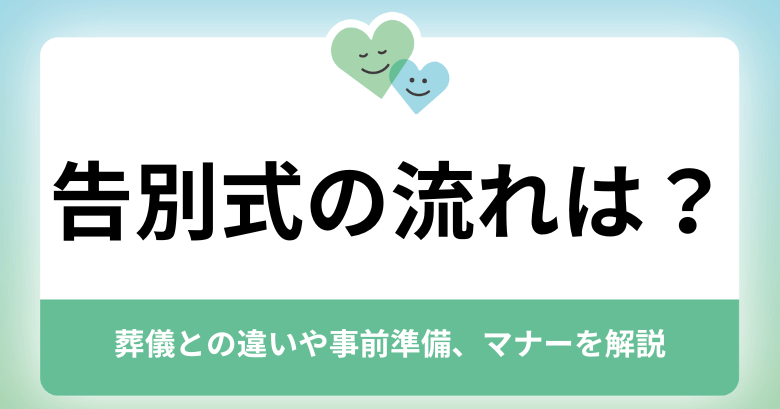※当記事はPRを含みます。
遺産分割協議書とは、すべての相続人が話し合いで決めた遺産分割の内容を記載した文書です。
各相続人の取り分を文書化することで、記憶や認識の違いによるトラブルを回避できます。また、全相続人の合意によって相続したことを証明する書類として不動産や預貯金、自動車、株式等の名義変更手続きに活用できます。
遺産分割協議書を作成する際の必要書類や、協議書作成までの流れについてご紹介しましょう。
- 遺産分割協議書の作成では事前に必要書類を揃える
- 遺産分割協議書の作成に際しては、必要書類として被相続人の生まれてから死亡するまでの連続したすべての戸籍謄本類を集める
- 相続手続きでは多くの場合遺産分割協議書が必要になる
遺産分割協議書の作成における必要書類
遺産分割協議書を作成するには、遺産をどのように分配するかについて、相続人全員で協議をして決める必要があります。
法的に有効なものとするために、遺産分割協議書の作成に際しては次の必要書類を用意します。
- 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書と実印
- 遺言書がある場合には遺言書
- 検認を受けた場合には検認済証明書
- 相続放棄者がいる場合は相続放棄受理証明書
それぞれの必要書類について具体的に説明していきましょう。
被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
遺産分割協議書を作成する際には、被相続人(亡くなった方)が生まれてから死亡するまでの連続したすべての戸籍謄本類を集めます。
戸籍謄本類は、被相続人が亡くなった時点の本籍地から遡って出生時の戸籍謄本類までたどる必要があります。それぞれの本籍地の役所で取得します。取得方法は、直接役所の窓口へ行く他に、郵送でも請求できます。
被相続人が結婚や離婚を繰り返した場合や本籍地を移転させていれば、入手すべき戸籍謄本類が多くなります。
戸籍謄本類に漏れがあると、遺産分割協議書にもとづく相続手続きはできません。すべての謄本類が連続していることによって、相続人が他にいないことが明らかになり、遺産分割協議書は有効な書面として扱われるのです。
戸籍謄本類には、次の3種類があります。
戸籍謄本
一般的に「戸籍」と呼ばれる現在の戸籍です。他と区別するときに「現戸籍(げんこせき)」と呼ぶことがあります。
除籍謄本
死亡や婚姻などで戸籍から抜けて全員がいなくなった戸籍は、除籍簿に綴られます。そこに綴られた戸籍を除籍と呼びます。
改製原戸籍謄本
電子化などで様式が変更された際の、それ以前の様式の戸籍です。
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
住民票の除票は、被相続人が亡くなった事実と、その時点の住所地を証明できる書面です。
様式は住民票と同じですが、書面の右上に「除票」と印字されています。記載されている事項は、住民票に記載される事項(氏名・生年月日・住所)に死亡年月日が加わります。マイナンバーの記載はありません。
被相続人の住民票の除票が市町村において廃棄されているなどの理由で取得できない場合は、戸籍の附票を取得します。
戸籍の附票とは、戸籍に付属しているもので、戸籍に記載されている人の住所が記載されています。
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本(しょうほん)が必要です。抄本とは、特定の人物の身分事項だけが記載された証明書です。
戸籍謄本や抄本を用意する際は、取得日が重要となります。被相続人が亡くなった日以後の証明がある書面でなければ有効ではありません。
相続人全員の印鑑登録証明書と実印
遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押します。
そのため相続人全員の印鑑登録証明書が必要です。各相続人の住所地の役場で申請します。印鑑登録をしていない相続人がいれば、すみやかに印鑑登録をする必要があります。
遺言書がある場合には遺言書
遺言書がある場合には、遺言書を用意します。遺言者が自ら書いた遺言書である自筆証書遺言であれば、多くの場合、自宅や貸金庫で保管されています。あるいは、法務局に預けられていることもあります。
公証人が作成した公正証書遺言の場合は、公証役場で検索すれば遺言書があるかどうかが分かります。自宅や貸金庫に保管されているのは、正本です。正本が見つからない場合は、原本が公証役場に保管されていますから、謄本の申請をします。
遺言書があれば、遺言書が遺産分割協議に優先されます。
しかし、次のような要件を満たしている場合には、遺産分割協議によって遺言書と異なる内容で遺産分割を行うことができます。
- 遺言書で遺産分割協議が禁止されていない
- 相続人と受遺者(相続人以外の遺産を受け取る人)の全員が合意している
- 遺言執行者が合意している
検認を受けた場合には検認済証明書
自筆証書遺言が法務局に保管されておらず、別の場所で発見された場合、開封する前に家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
検認が終了したら、「検認済証明書」を発行してもらいます。
相続放棄者がいる場合は相続放棄受理証明書
正式に相続放棄した相続人がいる場合は、家庭裁判所で「相続放棄受理証明書」を取得します。相続放棄が家庭裁判所に受理された以後に申請すれば発行してもらえます。
財産目録
相続財産の全体像をすべての相続人で共有するために、財産内容や評価額をまとめた財産目録を作成します。
遺産分割協議書が必要になる相続手続き
遺産分割協議書は、次の手続きの際に提出を求められます。
それぞれの手続きにおける、必要書類を紹介します。
預金相続手続きの必要書類
預金相続手続きは、次の書類が必要です。
- 遺産分割協議書または相続同意書
- 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書と実印
- 相続手続き依頼書
これらの必要書類を提出することより、すべての相続人が合意した遺産分割協議書であることが証明できます。
不動産相続手続きの必要書類
不動産の相続が発生した場合の必要書類は次のとおりです。
- 遺産分割協議書
- 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書と実印
- 固定資産税評価証明書
- 相続登記申請書
自動車の名義変更の必要書類
車の名義変更手続きをする際は、まず名義が被相続人のものになっていることを確認します。その後、相続人の協議で新しい所有者を決めて手続きをします。
自動車の名義変更は、次の必要書類を揃えて運輸支局で行います。
- 遺産分割協議書
- 車検証
- 車庫証明書
- 被相続人の戸籍謄本または除籍謄本
- 被相続人の戸籍の全部事項証明書
- 相続する人の印鑑登録証明書(発行から3カ月以内)
- 相続する人の実印の準備(あるいは委任状に実印を押印したもの)
有価証券相続の必要書類
株などの有価証券の相続手続きをするときの必要書類は、次のとおりです。
- 遺産分割協議書の写し
- 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書と実印
- 株式名義書換請求書などの書類
上場株式の場合は証券会社や信託銀行などを通しておこないます。非上場株式の場合は株式を発行している会社に手続きをお願いします。
相続税申告の必要書類
相続税の申告の際には、次の必要書類を税務署に提出します。
- 遺産分割協議書の写し
- 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書と実印
法定相続一覧図の活用を
相続手続きでは、ほとんどの機関窓口で「被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍」などの膨大な必要書類の提出が求められます。
これらの書類はいったん申請窓口で預かり、審査終了後に返却されます。そのため、これらの必要書類を1セットしか用意していない場合は、提出するたびに、他の手続きがストップすることになります。
相続手続きを複数の機関で同時に行いたい場合には、最初に法務局で「法定相続一覧図(相続関係を一覧にした図)」を作成してもらうという方法があります。
「法定相続一覧図」の謄本を必要部数分交付してもらい、それぞれの申請窓口に提出することで次の必要書類の提出は不要となります。
- 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書と実印
遺産分割協議書を作成する流れ
遺産分割協議書を作成する際は、まずすべての相続人の確認を行います。また遺言書がないことを確認します。
そのうえで相続人全員によって遺産分割について協議をして、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書作成の具体的な流れを順に紹介します。
遺言書を確認する
相続が発生したときは、最初に遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容が遺産分割協議より優先されます。
ただし、遺言書がある場合でも相続人全員が「遺産分割協議による遺産分割をしたい」という意見で一致するなど、一定の条件が揃えば、遺言書があっても遺産分割協議を行うことが可能です。
また遺言書を作成したときの方法や内容によっては、無効にできる可能性があります。
遺言書が存在した場合の遺産分割協議が有効かという判断や、そもそも遺言書が有効かという判断は、高度な専門知識を要します。お悩みの際は弁護士などの専門家に確認してください。
相続人の範囲を確定する
戸籍類などの調査により、すべての相続人を確定します。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。ひとりでも欠けていると、遺産分割協議は無効です。
相続人の範囲が確定したら相続人に連絡を取ります。連絡先の分からない相続人がいれば親族に確認するなど、あらゆる手立てを使って捜索する必要があります。
親族などに聞いても連絡先が分からない場合には、弁護士に相談して調査してもらいましょう。
相続対象となる財産を調査する
相続対象になる相続財産を調査します。
相続対象となるものとして、次のようなものがあります。
- 不動産
- 預金
- 現金
- 有価証券
- 動産(貴金属や美術品など)
- 相続可能な権利(著作権など)
相続人で遺産分割協議をする
相続人と相続財産の確認ができたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
協議といっても、一斉に同じ場所に集結する必要はありません。事情がある方は、電話やメールでのやり取りによって合意を得るという方法も可能です。
あるいは、相続人のひとりが代表して、他の相続人に遺産分割などの事項について説明をして同意を得るという方法でも問題はありません。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の書式に決まったルールはありません。内容を確認したうえで、全相続人が住所と氏名を記入して実印を押します。
遺産分割協議書の作成に困ったら専門家に相談を
遺産分割協議書の作成に際しては、相続財産を明白にするために財産目録を作成します。
また遺産分割協議書を法的に有効なものとするために、次の必要書類を用意します。
- 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書と実印
これらの必要書類は、 預金相続、不動産の相続登記、自動車の名義変更、有価証券の相続手続きにおいて、遺産分割協議書とともに、手続きをする窓口に提出する必要があります。
必要書類の提出を簡略化するために、法務局で「法定相続一覧図」を作成してもらい、その謄本を交付してもらうことも可能です。
遺産分割協議は、必ずしも一斉に会する必要はありません。電話やメールによって内容を理解してもらい合意を得ることも認められます。全員の合意を得られたら、遺産分割協議書を作成して相続人全員が住所と氏名を記入して実印を押します。
もし遺産分割協議で話し合いがまとまらない状況になったり、他の相続人の言い分に納得がいかなかったりする場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
ほかにもこちらのメディアでは、遺産分割協議書とは何かや遺産分割協議書の提出先についても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。