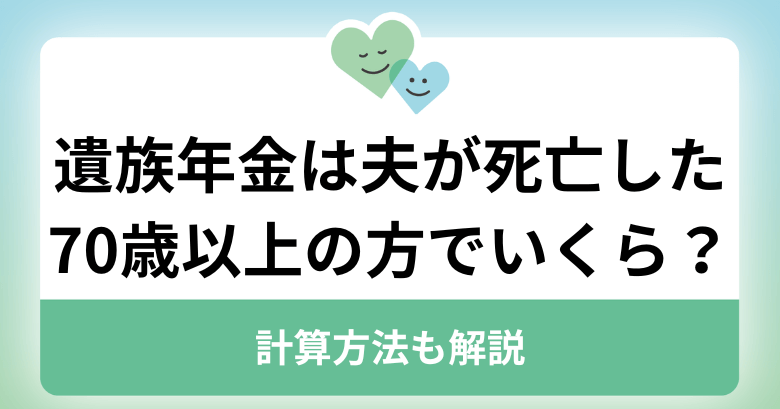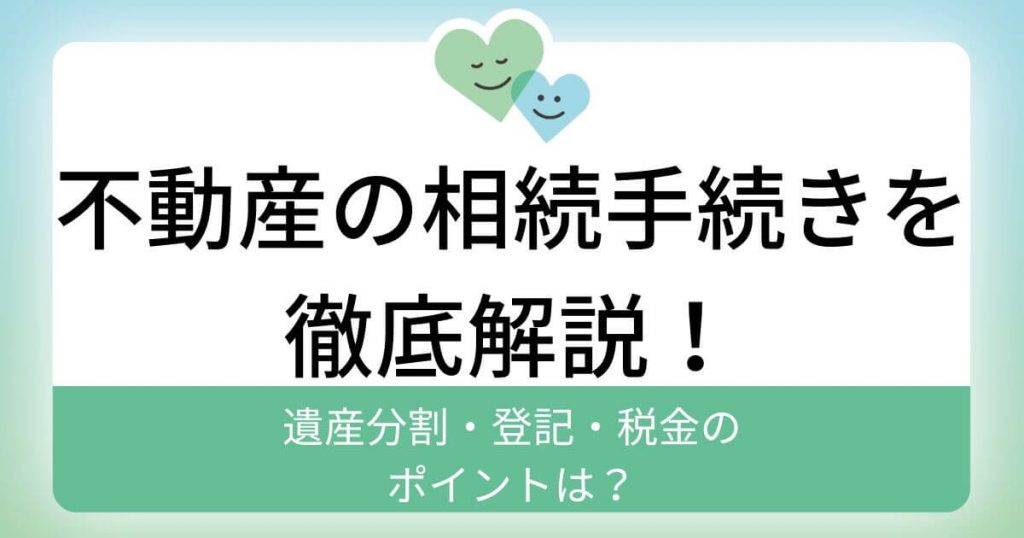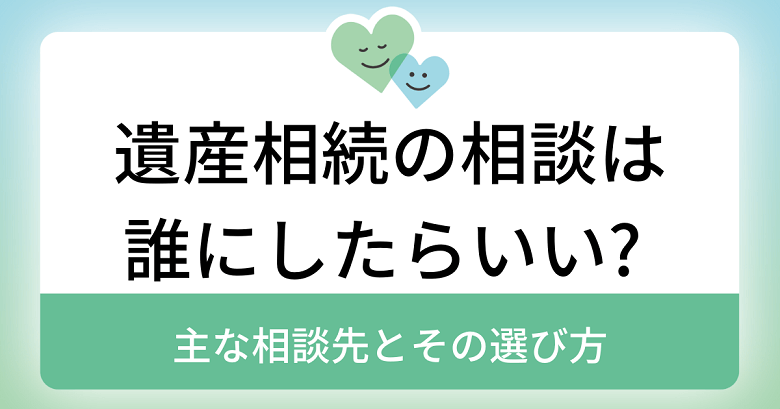※当記事はPRを含みます。
遺産のすべてを1人の相続人が独占していたり、第三者への莫大な遺贈があったりなど、遺言書の内容に納得できないケースもあるでしょう。
遺言書の記載内容を不公平だと感じた場合、不足分を金銭に換算して返還を求める「遺留分侵害請求」を行えます。この遺留分侵害額請求は、請求する側にとっても請求される側にとっても、高度な専門知識を要する難しい手続きです。
今回の記事では、この遺留分侵害額請求という遺産を守る手続きについて、わかりやすく解説していきます。
- 遺留分侵害額請求は、最低限の遺産をお金に換算して請求する手続き
- 遺留分算定の基礎には、生前贈与も含まれる
- 手続きの流れは協議、調停、審判。不安があれば弁護士に相談しよう
遺留分とは?
遺留分とは、兄弟・姉妹以外の法定相続人だけに認められた、最低限の遺産取得分です。
仮に財産を全く取得できない内容の遺言書が遺されていたとしても、遺留分に相当する遺産だけは受け取ることができるとされています。遺言書によっても侵すことができない、非常に強い権利といえるのです。
特定の相続人に認められた最低限の相続財産
相続財産の分割割合は法定相続分として法律に示されてはいるものの、遺言書に示された遺産の分割方法や贈与などの要因があれば、必ずしもその遺産を取得できるとは限りません。
遺言は法定相続分よりも優先されるため、仮に「すべての遺産を長男に相続させる」と遺言書に書かれていれば、その他の相続人は何も相続できなくなってしまいます。法定相続人だけでなく、全財産を第三者に譲ることも可能です。
しかしこれでは、いずれの財産も受け取れない相続人にとっては、極めて不公平と言わざるを得ません。
このため民法では、遺言書によっても侵すことができない「最低限の遺産を取得できる権利」として、特定の法定相続人に対して遺留分を定めているのです。
ただしこの遺留分は、「権利者が主張すれば手に入れることができる」という位置づけです。何もしなければ手に入らない性質のものであるとともに、遺留分を主張しないという選択も権利者に委ねられています。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められる相続人は、民法で「兄弟姉妹以外の相続人」と定められています。つまり配偶者と子、親などの直系尊属が遺留分を持つ法定相続人です。
相続開始時点で子がすでに亡くなっていた場合には、代襲相続によって被相続人の孫が相続人の立場となりますが、このケースでも遺留分は認められます。
一方、被相続人の兄弟・姉妹には遺留分が認められていないため、仮に代襲相続が発生しても甥・姪の遺留分も認められません。
相続人ごとの遺留分の割合
遺留分の割合は、法定相続分の半分が原則です。ただし、親などの直系尊属だけが相続人となる場合に限って、法定相続分の1/3とされています。
また遺留分を計算する際の法定相続分も、相続人の組み合わせによって変わる点にも注意が必要です。
配偶者と子ども2人が相続人である場合、配偶者の法定相続分は1/2、2人の子どもはそれぞれ1/4ずつです。この場合の遺留分はその半分、つまり配偶者が1/4、2人の子どもはそれぞれ1/8となります。
配偶者と被相続人の親が相続人であれば、配偶者が1/3(2/3の半分)、親が1/6(1/3の半分)です。
| 相続人の組み合わせによる遺留分の例 | |
|---|---|
| 配偶者のみが相続人 | 1/2 |
| 子のみが相続人 | 1/2 |
| 直系尊属のみが相続人 | 1/3 |
| 兄弟姉妹のみが相続人 | なし |
| 配偶者と子が相続人 | 配偶者1/4 子が1/4(子の人数で均等割) |
| 配偶者と父母が相続人 | 配偶者1/3 父母が1/6(父母で均等割) |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人 | 配偶者1/2 兄弟・姉妹なし |
遺留分の侵害とは?
遺産分割割合が法定相続分と大きく異なる遺言や、第三者への多額の遺贈などにより、遺留分に相当する最低限の遺産を受け取れない相続人が出る可能性があります。
遺留分を持つ相続人が受け取れる遺産額が、その最低限保障された額を下回ることが「遺留分の侵害」です。
遺留分の侵害が生じる事情はさまざまで、遺言書によるものだけとは限りません。どのような要因で遺留分の侵害が生じるかも知っておきましょう。
不公平な遺言
遺言は被相続人の意思を示す大切な方法といえますが、時として不公平な相続を招く可能性があることは否めません。遺言が遺留分侵害の要因となりがちなケースは、極端に偏った遺産分割割合や、第三者への多額の遺贈です。
特定の相続人にすべての財産を譲る意思表示や、法定相続人以外の第三者に多額の財産を遺贈する旨が記載されていれば、他の相続人が受け取れる遺産がゼロになったり、遺留分に満たないほど少なくなったりする可能性が生じます。
ただし、遺留分はあくまでも権利であり、必ずしも行使しなければならないという性質のものではありません。例え遺留分を侵害する内容の遺言書であったとしても、遺言そのものは有効です。
例えば、配偶者と子どもが相続人で、「配偶者にすべての遺産を相続させる」との遺言書があったとしても問題ありません。
実際に、このような遺産分割は頻繁にみられるものであり、遺留分を侵害された相続人がそれを許容できるのであれば、トラブルに発展することもありません。
死因贈与
死因贈与とは、贈与者(贈る人)と受贈者(贈られる人)の合意によって成立する贈与契約の1種です。ただし、その効果が発生するのは「贈与者が死亡したとき」に限定されているため、結果的には遺贈に似た効力を生じます。
死因贈与と遺贈では、発生する効果は似通ってはいるものの、法律行為の種類としては明確に区別されています。
遺贈は被相続人が遺言書に記載するだけで成立するのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の合意があってはじめて成立する法律行為だからです。
また、相続開始時で同時に効果が生じる行為ではありますが、死因贈与は被相続人の生前に契約が成立しているという点も大きな相違点です。
生前贈与
遺留分侵害の要因の中でも、少し複雑なのが生前贈与です。
生前贈与とは、被相続人の生前に財産を贈与することで、法定相続人への贈与だけでなく、第三者への贈与も含まれます。
ただし、遺留分を侵害する生前贈与とされるのは「相続開始時から1年以内の贈与」と、期間に制限が設けられているのも特徴です。
また生前贈与の中でも、推定相続人に対して行われた生前贈与のうち、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本」に当たるものは特別受益とされ、他の生前贈与と扱いが異なります。
特別受益に該当する贈与は、「相続開始時から10年以内」に行われたものが、遺留分侵害に算入されるのです。
通常の生前贈与と特別受益の違いを判断するのは少し難しいと思いますが、法定相続人に対して結婚資金や住宅購入資金を援助したケースなどが該当します。
推定相続人は、将来的に相続が発生すれば、遺産を受け取ることができる立場ですから、生前に受けた資金援助を「遺産の先渡し」と解釈するのです。
遺留分を侵害している生前贈与は、受け取った人の立場と金銭の性質によって、相続開始時から1年以内か10年以内かという判断が分かれることに注意が必要です。
また、贈与者と受贈者が遺留分を侵害すると知っていながら行われた贈与などに関しては、一切の期間制限を受けません。例え15年、20年前の贈与であろうとも、遺留分の算定に影響を及ぼすのです。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分を侵害された権利者は、多くの遺産を取得して遺留分を侵害している人に対して、遺留分に相当する金銭を請求できます。それが「遺留分侵害額請求」です。
遺留分侵害額請求は、侵害された遺留分に相当するお金を取り戻す手続きです。
例えば相続人が子ども2人のケースで、長男が1,000万円相当の自宅を相続し、次男の相続財産が何もなかったとしたら、次男は遺産の1/4に相当する250万円を長男に対して請求することができます。
- 長男:1,000万円相当の自宅を相続
- 次男:相続財産が何もなし
- 遺留分侵害額請求:次男は遺産の1/4に相当する250万円を長男に対して請求できる
侵害された遺留分を回復させる権利
遺留分侵害額請求は、「侵害された遺留分を金銭に換算して取り戻す仕組み」として、2019年7月の民法改正によって運用が開始された制度です。
この特徴は、侵害額に相当するお金を支払わせることにより遺留分を回復させる点で、かつて運用されていた現物返還の仕組みから、より現実的な制度へと生まれ変わりました。
遺留分減殺請求との違い
2019年7月の民法改正以前には、遺留分侵害額請求に相当する制度として「遺留分減殺請求」がありました。
いずれも「最低限の遺産を受け取れなかった場合に、遺留分を侵害している相手から不足分を取り戻す」という手続きですが、この2つには大きな違いがあります。
遺留分侵害額請求は「遺留分に不足する金額」を請求するのに対して、遺留分減殺請求は「侵害の原因となっている遺産そのもの、現物を返還させる」という点です。
- 遺留分侵害額請求:遺留分に不足する金額を請求する
- 遺留分減殺請求:侵害の原因となっている遺産そのもの、現物を返還させる
相続財産は何も現預金や現金だけとは限りません。不動産や株式など、分割が難しい資産も含まれます。分割が困難な資産を返還しようとした場合には、共有財産として扱う以外に手段がない可能性もあり得ます。
例えば相続財産が不動産だけで、それを1人に相続させたために発生した遺留分侵害であれば、遺留分減殺請求で取得できるのは「不動産の共有持ち分」という法律上所有権の過ぎません。
先ほどの相続人が子ども2人のケースで、相続財産が1,000万円の不動産という場面を想定してみましょう。
長男が不動産を相続し、次男の相続財産が何もなかったとしたら、次男は遺産の1/4に相当する遺留分が侵害されている状況に陥ります。
この場合、遺留分侵害額請求では「250万円の現金」を長男に対して請求できるのに対し、遺留分減殺請求で取得できるのは「不動産の1/4の共有持ち分」です。
- 長男:1,000万円相当の自宅を相続
- 次男:相続財産が何もなし(遺産の1/4に相当する遺留分が侵害されている)
- 遺留分侵害額請求なら:250万円の現金を長男に対して請求
- 遺留分減殺請求なら:不動産の1/4の共有持ち分を長男に対して請求
請求方法が現物から金銭に変わったことで、より現実的な解決が期待できるのです。
遺留分侵害額請求権の時効と除斥期間
遺留分侵害額請求権に時効があり、法律に定められた期間を経過すれば権利が消滅します。
これは民法第1048条に定められており、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与また遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも同様とする」とされています。
ただし「侵害があったことを知った時から1年」は消滅時効、「相続開始から10年」は除斥期間と解されており、法律上の扱いが多少異なる点には注意が必要です。
消滅時効と除斥期間は、「権利を行使せずに一定の期間が経過すると、権利自体が消滅する」という効果を生じる点では同じです。しかし、消滅時効は時間の経過とともに、当事者による時効の主張があって初めて効果を発揮するのに対し、除斥期間は期間の経過のみで権利が消滅します。
また消滅時効にはいくつかの時効を止める手段がありますが、除斥期間は権利を行使しない限り進行を中断させることができません。
| 消滅時効 | ・侵害があったことを知った時から1年 ・時間の経過とともに、当事者による時効の主張があって初めて効果を発揮 ・いくつかの時効を止める手段がある |
|---|---|
| 除斥期間 | ・相続開始から10年 ・期間の経過のみで権利が消滅 ・権利を行使しない限り進行を中断させられない |
遺留分侵害額請求権の時効を止める方法
遺留分侵害額請求権の時効を止めるには、「時効の完成猶予」もしくは「時効の更新」につながる行動をとらなければなりません。
完成猶予とは、時効の進行が一時的に中断され、時効の完成が先延ばしになること。一方の更新は進行していた期間がリセットされ、新たにゼロからスタートすることです。
- 完成猶予:時効の進行が一時的に中断され、時効の完成が先延ばしになる
- 更新:進行していた期間がリセットされ、新たにゼロからスタートする
つまり完成猶予と更新を比較すると、時効期間がリセットされる更新のほうがより強い効果を持つ方法であることが分かります。
しかし、時効の更新事由は「裁判上の勝訴が確定する確定判決」など、いずれも高いハードルの条件です。
このため遺留分侵害額請求権の時効を止めるには、催告(相手側に遺留分侵害額の支払いを請求すること)や、侵害額に関する協議を行う旨の合意、訴訟の提起などが現実的な策として挙げられます。
なお催告に際しては、遺留分侵害額の請求である旨や相手側に送達されたことを証明するために、配達証明付き内容証明郵便などを利用するとよいでしょう。
遺留分の計算方法
遺留分の額を知るためには、いくつかの手順を踏んで計算しなければなりません。
法定相続分とは算入する数値に違いがあるものも含まれますので、段階を追って正確な数値を求めましょう。
遺留分の基礎となる財産の額を算出する
前述した通り、遺留分の基礎となる財産は、相続開始時点での遺産だけとは限りません。1年以内の生前贈与や10年以内の特別受益を加算した額が総額となります。
ただし、相続財産に借金などのマイナスの財産がある場合には、その金額を差し引いて財産額を算出します。
- 相続財産+1年以内の生前贈与+10年以内の特別受益-債務=遺留分算定の基礎となる遺産総額
個別遺留分割合を乗じて遺留分の金額を算出する
遺留分の基礎となる金額を算出したら、それに個別遺留分を乗じて遺留分の金額を算出します。
個別遺留分の割合は法定相続人の組み合わせによって異なります。
前に記載した「相続人の組み合わせによる遺留分の例」の表に当てはめて確認してみましょう。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求する手続きの流れは、まずは当事者同士の話し合いによる解決を目指し、合意に至らなければ司法の場に委ねるという流れです。
協議、調停、訴訟と、段階を追って進めます。
協議による解決
協議による侵害額の請求は、言ってみれば遺産分割協議と同様です。まずは遺留分を侵害している相手に対して、遺留分を侵害している事実とその金額、侵害額請求の意思を伝えましょう。
遺留分侵害額請求という名称から、ともすれば対立の図式を想像しがちではありますが、穏便な協議ができないと言い切れるわけではありません。相手方がそもそも遺留分を侵害している事実を認識していない可能性も十分に考えられるのです。
協議に応じてくれるのであれば、遺留分侵害額を補償してほしい旨を伝えて、円満な解決を目指しましょう。
内容証明郵便の送付
遺留分という強い権利が侵されている状態ですから、必ずしも相手側が協議に応じてくれるとは限りません。
相手が話し合いに応じない場合や請求に対する合意が得られない場合には、裁判所の力を借りて合意形成を目指す手続きに移ります。
しかしその前に行うべき重要な手続きが、時効の進行を止める「催告」です。
遺留分侵害額請求権の時効は「侵害があったこと知った時から1年」と定められています。時効の進行を止めるためには、遺留分侵害額を請求する旨の「催告」をしなければなりません。
遺留分侵害額の請求である旨を明記した内容証明郵便を送り、請求の事実と請求内容の証拠を残しておくことが必要です。
遺留分侵害額請求調停の申し立て
当事者だけでは遺留分侵害額請求の合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用します。遺留分を持つ相続人、もしくはその承継人が相手側の住所地の家庭裁判所に申し立てをするのです。
遺留分侵害額の請求調停は、裁判官や有識者で構成される調停委員会が当事者双方から事情を聴き、解決案の提示や助言などで双方の合意を目指す手続きです。
一般的に調停は1~2カ月に1回のペースで開かれます。当事者同士が顔を合わせることはなく、双方が主張や証拠などを調停委員に伝えながら合意形成を進めます。
複数回にわたってお互いの主張をすり合わせる作業を繰り返し、合意に至った場合には調停成立となり、その内容を記載した「調停調書」が作成されます。
この調停調書には裁判上の確定判決と同じ効力があるため、相手方が合意内容に則した義務を履行しない場合には、強制執行を行うことができるのです。
なお、2019年7月1日以前に開始された相続では、この申し立てはできません。旧民法の規定に基づき、遺留分減殺による物件返還請求等の調停を利用します。
遺留分侵害額請求訴訟
遺留分侵害額の請求調停でも双方の合意に至らず、不成立となった場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
遺産分割協議が整わなかった場合の手続きは、調停、審判、訴訟の順ですが、遺留分侵害額の請求には審判はありません。調停が不成立となった場合でも、自動的に訴訟に進むわけではなく、あらためて訴訟の手続きを取らなければならないことも覚えておきましょう。
遺留分侵害額請求訴訟を管轄するのは、家庭裁判所ではなく地方裁判所です。被告(相手側)の住所地の地方裁判所に対して訴えを起こします。ただし、請求額が140万円を超えない場合には簡易裁判所に訴えることができます。
遺留分侵害額請求訴訟では、原告(請求者)に立証責任があるとされています。つまり、遺留分算定の基礎となる財産額や、被告(遺留分を侵害している相手方)が取得した遺産の額や内容、原告の遺留分が侵害されている事実やその額などの証拠を用意しなければなりません。
これに対して被告は、原告の請求額や財産評価に対する反論などを提示していくのです。
裁判所は双方の主張を検討して判決を出しますが、訴訟の決着が必ずしも判決であるとは限りません。裁判所が和解案を提示し、双方の和解を促すのが一般的です。
この場合には、和解内容が記載された和解調書が作成され、訴訟は終了します。和解に至らなければ、裁判所が判決を言い渡すのです。
調停調書と同様に、和解調書も裁判上の確定判決と同じ効力を有しています。
遺留分侵害額請求に関わる相続税
遺留分は相続財産の一部と考えられますから、遺留分を受け取った人には相続税が課される可能性が生じます。遺留分侵害額請求によって取得した場合も同様です。
ただし、相続税の申告期限は相続開始から10カ月です。
よほどスムースに遺留分侵害額請求の手続きが進み、合意に至ったというケースを除いては、相続税申告前に遺留分の精算を完了するのは難しいかもしれません。
仮に申告前に遺留分の精算が完了したら、返還した遺留分を加味した相続割合で、相続税の申告を行えばこと足ります。
一方で、相続税の申告後に遺留分を返還した場合、遺留分を取得した権利者には修正申告や期限後申告の義務が、遺留分を支払った義務者には更正の請求の権利が発生します。
このため遺留分が侵害されているという事実がある場合には、遺留分の返還がされていない金額を基礎として、例え納めるべき税額がゼロであっても相続税の申告をしておくのが望ましいでしょう。
そのうえで、遺留分に関する合意が成立した段階で、修正申告や更正の請求の手続きを取るという手順です。
もっとも実務上は、必ずしもこの手続きを取らず、相続税相当額分について考慮した金額を提示したり、当事者間で精算したりという方法でも対応するケースも少なくないようです。
申告期限までにいったん申告と納税を済ませていたら、相続税納付の義務自体は履行を完了しているという考え方によるものといえるでしょう。
しかし、遺留分を返還した義務者が更正の請求を行えば、遺留分権利者にその分の税額を負担する義務が生じます。当事者間で清算した相続税相当額が、贈与とみなされる可能性もないとは言い切れません。
遺留分の返還によって相続税の納付義務が生じるケースでは、税理士などに相談することをおすすめします。
遺留分侵害額請求を依頼すべき専門家
遺留分侵害額の請求では、算定の基礎となる財産の評価から遺留分侵害が発生した要因の特定、相手方との合意形成に至るまで、相当な専門知識を必要とする手続きが待ち受けています。
特に合意形成が円滑に進まない場合には、調停や訴訟なども想定しておかなければなりません。
このため遺留分侵害額請求に関わる手続きを専門家に委ねたい場合には、弁護士に依頼するのが最も理にかなっているといえるでしょう。
なぜなら遺留分権利者の代理人として調停や訴訟で主張を代弁できるのは、弁護士に限られているからです。
弁護士に依頼した場合の費用
弁護士に遺留分侵害額請求を依頼した場合の費用は、「依頼人が受ける経済的利益」を基準として定められているのが一般的です。
しかし、弁護士費用は現在は完全に自由化されており、相場といえる指標がありません。
かつて日本弁護士連合会が報酬規程を定めていた経緯があり、現在も旧報酬規程をベースに報酬を定めている弁護士が多く存在しています。このため旧報酬規程が、1つの目安になるといえるでしょう。
| 日本弁護士連合会旧報酬規程 | |
|---|---|
| 300万円以下 | 着手金8%(最低10万円) 報酬金16% |
| 300万円~3,000万円 | 着手金5%+9万円 報酬金10%+18万円 |
| 3,000万円~3億円 | 着手金3%+69万円 報酬金6%+138万円 |
| 3億円以上 | 着手金2%+369万円 報酬金4%+738万円 |
遺留分侵害額請求を受けた場合に確認すべきポイント
逆にご自身が遺留分侵害額の請求を受けた場合、どのような対応をすべきでしょうか?
遺留分は特定の相続人だけに法律で保障された、最低限の遺産を受け取れる権利です。その請求が正当であるならば、支払う必要があります。
とはいえ、単に相手の請求を鵜呑みにすればよいというわけではありません。
相手が遺留分権利者に間違いないか、遺留分の算定は適切かなど、さまざまな視点から請求の内容を確認していかなければならないのです。
これらの手続きには、法律上の知識や相続に関わる慣習などの知識が不可欠です。手続きに不安がある場合には、早めに弁護士への依頼を検討しましょう。
遺留分を主張する人の正当性
遺留分を主張できる遺留分権利者は、被相続人の配偶者や子ども、親など、兄弟・姉妹以外の法定相続人に限られています。
遺留分を主張する相手がこの要件に該当しているかを、まず確認しなければなりません。
また、遺留分を取得できなかった要因が、「相続欠格」や「相続廃除」である可能性にも着目しなければなりません。これらに該当して相続権を失った場合には、遺留分の権利も失われているからです。
相続欠格は、遺産を手に入れるため不法行為を行った場合に該当します。この場合には、被相続人の意思に関わらず、強制的に相続人の権利を失うのです。
欠格事由は、民法第891条に以下の5つが定められています。
- 被相続人や先順位の相続人の殺害・殺害未遂で刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴をしなかった者
- 詐欺や強迫によって遺言をさせた、または撤回、取り消し、変更を妨げた者
- 詐欺や強迫によって遺言の撤回、取り消し、変更をさせた者
- 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
一方の相続廃除は、被相続人の意思に基づいて相続権を剝奪する制度です。
「被相続人に対する虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」などがあり、家庭裁判所に認められた場合に相続人の権利を失います。
請求額の妥当性
遺留分侵害額を請求された場合には、その請求額が争点となる可能性もあるでしょう。
遺留分の算定は複雑ですから、生前贈与の額や被相続人の債務などを考慮して、計算が正確であるかも確認しなければなりません。
相続財産は、現預金などのように評価額が確定的なものばかりとは限りません。不動産のように、評価額の算出方法によって価額が異なるケースもあり得えます。
「遺留分権利者が主張する請求額が妥当であるか」という点も、確認しなければならない事項です。
財産評価は適切か
遺留分侵害額請求において、請求する側とされる側の主張が食い違う原因の1つが財産評価の差異といえるでしょう。不動産や美術品のように、評価額の算出方法によって価額に大きな差異が生じる財産も少なくないからです。
どの評価方法を採用するかという問題は、「どちらが正しい」といった明確な結論が出るものではなく、合意形成の障害になりがちなポイントです。双方が自分にとって有利な方法を採用するでしょうし、どちらも正当な評価方法といえるからです。
このような主張を合理的にまとめるためには、弁護士に相談して対策を講じることが望ましいでしょう。
特別受益はないか
請求額の妥当性を考えるうえでは、遺留分侵害の要素となっている遺産の額だけでなく、それを相殺する特別受益がないかを確認することも大切です。
遺留分を算定する際に考慮する特別受益は、相続開始から10年以内という長い期間が対象です。その間に遺留分権利者が特別受益に当たる贈与を受けていた場合には、「すでに取得している相続財産」と考えることができるのです。
仮に相続時点では何の財産も取得しなかったとしても、すでに遺留分以上の財産を受け取っている可能性もあり得ます。
時効の成立
遺留分の侵害を主張された場合には、遺留分侵害額請求の時効についても確認すべきでしょう。
遺留分侵害額請求権は、遺留分の侵害を知ってから1年で消滅時効にかかります。請求された時点でその期間を過ぎていれば、時効の主張によって請求権を消滅させることができるのです。
また、遺留分侵害額請求の除斥期間は10年とされているため、相続開始や遺留分侵害を権利者が知らなかったとしても、相続開始から10年経過で権利が消滅するのです。
遺留分は相続トラブルを招きやすい要素
遺留分の問題は、そもそも不公平な遺産分割や贈与に起因するため、相続人同士のトラブルにつながりやすく、かつ解決が難しくなりがちな要素です。
法律に保証された最低限の遺産すらも取得できない相続人にとっては、とても容認できないものかもしれません。
その一方で、遺留分を侵害する遺言書を作成した被相続人や取得した相続人にとっても、重大な理由に基づく合理的な判断である可能性も決して低くはないのです。
どちらにも正当性が認められることが、トラブルを大きくする原因ともいえるでしょう。
遺留分に関する相談は早めに弁護士へ
遺留分に関する問題を解決するには、専門的な知識が非常に大切です。当事者同士の力で解決することができず、司法の場などで解決策を探る可能性も考慮しておかなければなりません。
もし遺留分を侵害された、遺留分侵害額を請求されたなどの問題が生じた場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
ほかにもこちらのメディアでは、法定相続人が相続放棄した場合についてや推定相続人についても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。