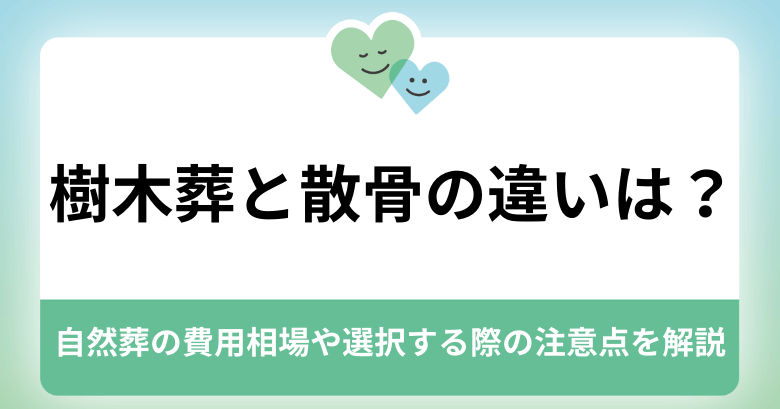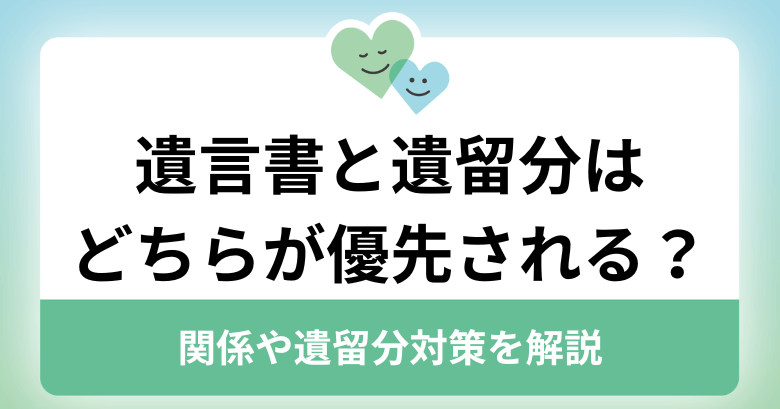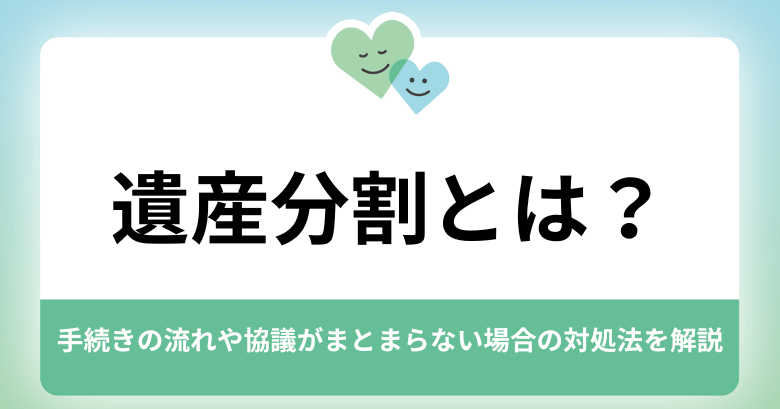
※当記事はPRを含みます。
相続の中で行う遺産分割という手続きが、今一つ正確に理解できない方は多いのではないでしょうか?
遺産分割とは、相続開始後に相続人全員の共有状態になっていた遺産を、現実的な形で分配する手続きです。株式のように名義変更が必要な財産は、遺産分割を経なければ活用できないケースも少なくありません。
今回の記事では、遺産分割の方法や手続きの流れを詳しく解説します。協議がまとまらない場合の対処法などにも触れるので、遺産分割に不安がある方はぜひ最後までお読みください。
- 遺産分割とは、相続人全員の共有状態となっている相続財産を現実的に分配する手続き
- 遺産分割の手法は現物分割・換価分割・代償分割の3種類
- 遺産分割を円滑に進めるには、相続人同士の妥協点を見出す努力が不可欠
遺産分割とは相続財産を分ける手続き
遺産分割とは、相続開始後に「すべての相続人の共有」という状態になっていた相続財産を、それぞれの相続人に実際に分配する手続きです。
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産は「相続財産」として、法定相続人が共有している状態となります。預金や不動産、自動車などのプラスの財産はもちろん、ローンや未払いの税金などのマイナス財産も含め、すべてが法定相続分に応じた持分割合による共有です。
法律的には問題のない状態ではありますが、すべての財産を複数人が共有している状態は、現実的には好ましくありません。例えば故人の自宅を相続人Aと相続人Bが1/2ずつで相続しながら、実際には相続人Aが単独で使用した場合、相続人Bにはメリットがなく不公平な状態となります。
相続人Bにしてみれば、「不動産の1/2の所有権を相続するよりも、代わりの財産を受け取りたい」と考えるのが通常ではないでしょうか?
このようなケースで、すべての相続財産を対象に、現実的に分割しやすい方法で相続人に分配する手続きが遺産分割です。
遺産分割と相続の違いが今一つ不明確であったのならば、「相続の中で、財産を分割する手続きが遺産分割」と考えればわかりやすいでしょう。
遺産分割の方法は3種類
相続財産に含まれるのは、預金や現金のように分割しやすいものだけとは限りません。先に例示した不動産のように、物理的な分割が難しい財産が含まれるケースは数多くあります。
さまざまな種類の相続財産を合理的に分配するために、主に「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つの手法が用いられます。
分割対象となる財産の種類や、相続人の希望に応じて取るべき方法が異なりますから、それぞれの手法の特徴や採用すべき場面をみていきましょう。
現物分割
現物分割とは、相続財産をそのままの形で分割する方法です。現金や預貯金のように分割が容易な財産に用いられるほか、「不動産を相続人Aが、預貯金を相続人Bが相続する」などのように、種類の異なる相続財産を分割する形でも使われます。
現物分割の最もわかりやすい例が現金です。仮に総額1,000万円の現金を被相続人の子どもである相続人AとBの2人で分割するのであれば、法定相続分どおりに分割すれば500万円ずつになります。お金の場合には、単純に割合で分割することが可能なため、現物分割が適しているのです。
不動産のような実物資産であっても、現物分割は不可能ではありません。例えば建物がない1筆の土地を相続する際に、分筆することで分割が可能だからです。
ただしこの場合、測量や分筆に伴う費用が発生するほか、広い土地を細分化したことで価値の低下を招く恐れがあることを知っておかなければなりません。
換価分割
分割の対象となる相続財産を売却し、その代金を相続人同士で分割する手法が換価分割です。現物分割が難しい資産や、相続人がその財産自体を必要としない場合などに多く用いられます。
先の現物分割と同様に、更地の土地を相続人2人で分割するケースを想定してみましょう。
分筆によって物理的な分割も可能ではありますが、そもそもその土地を2人の相続人が必要としていなければ、わざわざコストをかけて分筆するメリットはありません。
細分化して資産価値の低下を招くくらいであれば、そのままの形で売却して、そのお金を相続割合に応じて分配したほうが合理的です。
不動産を相続する場面などで多く用いられる手法ですが、売却する資産によっては、現金化までに長期間を要する可能性も否めません。このため、相続税の申告期限に間に合わないなどのリスクも考慮しておく必要があります。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が特定の遺産を取得する代わりに、他の相続人に対して「代償金」を支払う分割の方法です。価値の高い資産を得た相続人が、他の相続人に差額分を補填することで公平性を保ちます。
相続人AとBが1/2ずつの割合で土地を相続する場面を例に挙げれば、相続人Aが土地を取得し、その価値の半額にあたるお金を相続人Bに支払います。
仮に土地の価値が1,000万円であったとしたら、相続人AがBに対して、持ち分の価値に相当する500万円を支払えば不公平は生じません。
つまり代償分割は、特定の遺産を取得する相続人が、他の相続人が所有する共有持ち分を買い取る仕組みと理解すればわかりやすいでしょう。
代償分割では、対象の遺産の評価額に関するトラブルに注意しなければなりません。評価額は代償金の額に直結するため、双方の認識が一致しなければ合意にいたるのは難しいといえます。
また、不動産のように高額な遺産の場合、必要とされる代償金が高額になりがちな点にも注意が必要です。
遺産分割を行わないリスク
遺産分割は、「複数の相続人が取得しやすい形に相続財産を分ける」という手続きですから、法律に定められた義務などではありません。しかし、遺産分割を行わずに放置していた場合には、さまざまなリスクが生じます。
前述したとおり、遺産分割前の相続財産は「共同相続人全員で共有している状態」です。被相続人の子どもであるAとBが相続人であれば、現預金も株式も、さらには負債に至るまで、すべて1/2ずつの持ち分を保有している状態といえます。
この状態でAかBのいずれかが亡くなり二次相続が発生したら、共有の持ち分はさらに細分化してしまいます。遺産に不動産などがあれば、将来的に売却をしようと思っても、それが困難になる可能性が否めません。
共有財産を売却しようとすれば、所有者全員の合意が必要だからです。
一方で、自己が所有する持ち分だけであれば、他の所有者の意向に関わらず自由に処分できます。共有者の1人が第三者に持ち分を売却してしまえば、全体の処分がさらに難しくなるリスクも生じるのです。
遺産分割を行う流れ
相続開始から遺産分割を行うまでには、さまざまな段取りを経なければなりません。相続は、法律によって厳格に定められた手続きだからです。
法律に則した相続人を確定し、分割すべき遺産を明確にしなければ、後にトラブルを招く懸念も否定できません。
遺言書の確認
遺言書とは、相続や財産の処分などに関する被相続人の意思を記した法律上の書面です。法的な効力があり、遺言書がある場合にはそれに従うのが原則とされています。このため遺産分割を行う前に、遺言書の有無を確認することが鉄則です。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。このうち法務局で保管されていた自筆証書遺言と公正証書遺言以外は、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があることを覚えておきましょう。
検認は、見つかった遺言書が真正なものであることを証明する手続きです。
相続人の調査・確定
相続財産の分配に際しては、遺産を受け取る相続人が誰であるかを正確に把握しなければなりません。被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどって相続人になり得る立場の方をすべて抽出し、民法に定める相続順位に従って相続人を確定します。
相続順位は、第1順位が子・孫などの直系卑属、第2順位は父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。なお、配偶者には順位がなく、常に相続人になる立場とされています。
先の順位の方が相続人になると、後の順位の方は相続人にはなりません。被相続人に配偶者がいれば「配偶者と子ども」「配偶者と被相続人の親」など、配偶者と相続順位が上位の方の組み合わせで相続人が決まります。
相続財産調査・財産目録の作成
遺産を受け取る相続人を確定するのと並行して、存在する相続財産を詳細に調査し、すべての遺産を確定しなければなりません。
相続とは、亡くなった方の財産上の権利・義務のすべてを引く次ぐ行為です。財産上の義務には、「借金を返済する義務」なども含まれます。
つまり、現預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めすべてを網羅した一覧を作成する必要があるのです。
すべての資産と負債を正確に調査するには、時間と労力だけでなく、専門知識も必要とされます。
特に借金などの負債が資産を上回っている場合には、相続放棄などの手続きを取らなければ、返済の義務を引き継ぐ恐れがあることを理解しておきましょう。
- 現金
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 株式
- 債権
- 保険
- 電子マネー
- FX
- 仮想通貨
- 貴金属
- 美術品
- 家具・家電類
- 借入金
- 分割払い・リボ払い
- 保証債務
- 未払いの税金・保険料
遺産分割協議
遺産分割協議とは、すべての相続人が参加して、相続財産の分け方を決める手続きです。すべての遺産が相続人全員の共有となっている状態を解消し、現実的に受け取れる状態にするための話し合いといえばわかりやすいでしょう。
子ども2人が相続人であれば、自宅不動産を相続人Aが取得し、現預金と株式を相続人Bが所有するなどの方法で、それぞれが取得する財産の種類や割合を決めます。
法定相続分が1つの目安になりますが、相続人全員の合意があれば必ずしも従う必要はありません。
被相続人の妻と2人の子どもが相続人となったケースでは、子ども2人が相続分の受け取りを放棄し、妻が全財産を相続するなども珍しくはない事例です。
ただし遺産分割協議には、相続人全員の参加が必須ということを覚えておきましょう。仮に相続人が遠方に住んでいて一堂に会することが難しいとしても、手紙や電話、メールなどを用いて全員の合意を得ることが必要です。
1人でも相続人が欠けていた場合には、その遺産分割協議は無効です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で相続財産の分割の方法が決まったら、書面を作成して記録として残す必要があります。この書面が遺産分割協議書です。
遺産分割協議書に記載する内容は、被相続人の氏名や住所、死亡日といった相続を特定する内容、財産を特定する内容、分割方法などです。さらに、その内容で相続人全員が合意している旨も記載しなければなりません。
遺産分割協議書の意味は大きく分けて2つあります。1つは「相続人全員が合意した証拠」で、もう1つは「合意した内容を第三者に示すための証拠」です。
一旦は合意に至った遺産分割方法でも、時間の経過とともに不満を持つ相続人が出たとしても不思議はありません。このため合意した証しを残しておく必要があるのです。
また、遺産分割協議に基づいて財産を取得する場合には、それを第三者に示さなければならないケースが生じます。不動産を単独で相続する場合などがわかりやすいでしょう。
複数の相続人がいるにも関わらず、相続した不動産を単独名義で登記するためには、他の相続人がそれに合意していることを証明しなければなりません。このため相続登記の際に、遺産分割協議書の添付が必要とされるのです。
遺産分割協議がまとまらない場合の対処法
すべての相続の場面で、遺産分割協議が円滑に進むとは限りません。
ご自身が受け取るべき遺産額の主張が食い違ったり、長らく疎遠になっていた相続人が協議に応じてくれなかったりするケースも往々にして生じます。
遺産分割協議がまとまらない場合の対処法についても、あらかじめ把握しておきましょう。
遺産分割調停
当事者だけで遺産分割の話し合いがまとまらない場合や、そもそも遺産分割協議に応じない相続人がいる場合などには、司法の力を借りて合意形成を進められます。遺産分割調停がその第一の手続きです。
遺産分割調停は、遺産分割が進まない状況の相続人が他の相続人全員を相手として家庭裁判所に申し立てる仕組みです。
裁判官と調停委員で構成される調停委員会が、当事者の事情を個別に聞き取り、必要に応じて相続財産の資料や鑑定などを参考にして解決案を提示します。
ただし、ここで提示されるのはあくまでも解決案ですから、強制力があるわけではではありません。
遺産分割審判
話し合いがまとまらず遺産分割調停で不成立になった場合には、自動的に遺産分割審判に移行します。調停とは異なり、ここで示された結論には強制力があるため、審判に従わない相続人の財産の差し押さえなども可能です。
「強制力があるならば、最初から調停を行わずに審判を申し立てたい」と考える方もいるかもしれませんが、残念ながらそれは認められません。
「調停を行える事件については、訴えの前に調停を申し立てなければならない」とという、調停前置主義が取られているからです。
また、相続人の主張を裏付ける証拠などは、ご自身で用意しなければなりません。仮に「他の相続人が遺産を隠している」と主張したとしても、裁判所がその財産を探してくれるわけではないのです。
遺産分割を行う際の注意点
遺産分割を行う際には、法に定められたルールを守ることはもちろん、協議を円滑に進めるためのポイントを抑えておかなければなりません。
特に注意すべき点を列記します。
遺産分割協議は全員参加が必須
遺産分割協議が正当に成立するには、相続人全員が参加していることが必須です。例え長らく音信不通になっている相続人がいたとしても、必ず連絡を取って参加してもらわなければなりません。
相続人を確定する際には、法定相続人に関する正しい知識を持つことが不可欠です。例えば被相続人に離婚歴があり、前妻の間の子どもがいたとしたら、その方(被相続人の子ども)も当然に法定相続人となります。
他の相続人と全く面識がなかったとしても、戸籍の附票などを頼りに住所を探し出し、遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。
生前の贈与を考慮
遺産分割を円滑に進めるためには、公平な遺産配分を原則とした考え方が基本です。ただし、特定の相続人だけ被相続人の生前に贈与を受けていた場合などには、その金額などを考慮する必要があります。
総額1,000万円の預金を残して被相続人が亡くなり、子どもである相続人AとBの2人が分割する場面を想定してみましょう。法定相続分どおりに分割すれば500万円ずつで、通常であれば円滑に合意に至るかもしれません。
しかし相続人Aだけが、マイホームを購入する際に500万円の資金援助を被相続人から受けていたとしたらどうでしょう?
500万円ずつ遺産を分配すると、実際には相続人Aが1,000万円を受け取っているのに対し、相続人Bは500万円しか受け取れません。この場合には、相続人Aが250万円、相続人Bが750万円の遺産を取得したほうが、むしろ公平になるともいえるのです。
また税法上でも、一定の期間内に相続人が生前贈与されていた財産については、相続財産に加えて相続税を課すこととしています。
2024年1月1日以後の贈与からは、死亡日以前3年間だった加算の期間が7年間に延長されることも知っておきましょう。
遺言書と異なる分割も可能
遺言は故人の意思として最大限に尊重されますが、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる方法で分割することも可能です。ただし「遺産分割を禁止する」旨の遺言がある場合には、相続人の合意があっても遺産を分割できません。
遺言書と異なる遺産分割に関する定めは、民法907条と908条に明示されています。
907条で「共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合または分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも遺産を分割できる」と定めるとともに、908条で「相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる」と規定しているのです。
また、遺言で相続人以外の遺言執行者が定められている場合は、相続人全員とともに遺言執行者の同意も必要です。
遺産分割協議完了後の撤回は困難
一旦成立させた遺産分割協議を撤回することは、法律上は可能です。 ただしこの場合には相続人全員の合意が不可欠で、1人でも反対者がいれば撤回はできません。現実的には、非常に困難といえます。
ただし、 相続財産の調査が不十分だったり、特定の相続人が故意に財産を隠したりして、遺産分割の対象となる相続財産に誤りがあった場合は例外です。上記のケースでは、遺産分割自体の無効を主張できる可能性があります。
また、脅迫によってやむを得ず合意した場合なども同様です。
未成年者や認知症の方がいるなら代理人が必要
相続人の中に、未成年の方や認知症の方がいる場合には注意が必要です。
遺産分割は「相続する具体的な財産を決める」という、相続人の権利に関する重大な手続きです。取得する財産と放棄する財産に関する約束を相続人同士で交わす、いわば契約行為の一種ともいえます。
このため未成年者や認知症によって十分な判断力を持たない方などは、遺産分割を行う際に代理人を選任しなければならないのです。
未成年者の法定代理人は親とされているため、一般的な契約行為であれば親が代理人を務めれば問題ありません。しかし相続の場合、親と子どもの双方が相続人であれば、利害が対立するかもしれません。
このため親と未成年の子どもがともに相続人となっているケースでは、利害関係のない第三者を特別代理人に選ぶため、家庭裁判所に対して選任を申し立てる必要があります。
遺産分割で発生しがちなトラブル事例
慎重に遺産分割を進めたとしても、避けられないトラブルが生じるケースは少なくありません。
遺産分割で発生しがちなトラブル事例を把握し、その対処法についても知っておきましょう。
連絡が取れない相続人がいる
音信不通の相続人がいる場合、戸籍の附票などを頼りに住所を特定しても、連絡がつかない可能性もあり得ます。この場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。
不在者財産管理人とは、行方不明の相続人の代わりに遺産を管理する人です。あくまでも受け取った相続財産の管理責任を負うのが原則ですが、一定の手続きをすることで遺産分割協議にも参加できます。
また、行方不明の相続人が何年も生死不明の状態であるときは、失踪宣告の申し立てを行います。
失踪宣告とは、長期間に渡って生死不明の方を、法的に死亡したものとみなす制度です。この場合には、その相続人が死亡していることを前提とした相続関係で遺産分割を進めます。
評価額の意見が一致しない
相続財産は、現金のように価値が明確な財産だけとは限りません。財産の評価には複数の手法が用いられるため、相続人ごとに評価額の見解が一致しないケースが往々にして生じます。
評価額の算出方法によって金額が変わる財産の例を挙げるならば、不動産がわかりやすいでしょう。
一般に市場で取引される価額に比べて、相続税の算出に用いられる評価額が7~8割程度に抑えられるのが通常です。
つまり、市価を基準に評価額を認識している相続人と、相続税を根拠に評価額を認識している相続人では、その金額に大きな差異が生じます。
評価方法によって価額が変わる財産を含む遺産分割を円滑に進めるには、相続人が根拠の正当性を主張するだけでなく、妥協点を見出す努力が不可欠といえるのです。
遺産分割完了後に遺産が見つかった
すべての遺産分割が完了したと思ったあとに、気付かなかった財産が出てくるケースは珍しくはありません。この場合、新たに見つかった財産を対象に、遺産分割を行うのが原則です。
ただし実際には、遺産分割協議の場で「遺産分割完了後に新たな遺産が見つかった場合の対処」においても合意しておくことが望ましいでしょう。
例えば、遺産分割協議書に「遺産分割協議書に記載していない相続財産が判明した場合には、相続人Aが取得する」などの文言を記載しておくことも有効です。
遺産分割協議書の作成のポイント
遺産分割協議で合意に至った内容を記載する遺産分割協議書には、特定の書式などが定められていません。ただし、対象とする相続を特定し、遺産分割の内容が明確に示されている必要があります。
「相続人全員が合意している証拠になること」「合意した内容を第三者が明確に理解できること」という2点が作成のポイントです。
実印で押印し印鑑証明書を添付
遺産分割協議書には、相続人全員が署名したうえで実印を押印し、印鑑証明書を添付するのが原則です。
合意した相続人を明らかにするには、「記名・押印で足りる」とされています。つまり、認印での捺印も制限されていません。しかし実際には、認印では証拠としての能力が不十分といえます。
遺産分割協議によって分割方法を決める場合には、例え遺産の総額に対する割合が法定相続分どおりだったとしても、特定の相続人が特定の財産を得る代わりに一定の権利を放棄するという約束が盛り込まれているのが一般的です。
例えば「自宅不動産の所有権」という重大な権利を放棄するのであれば、その意思を証明するために実印と印鑑証明書が不可欠なのです。
相続財産が1,000万円の預金と評価額1,000万円の自宅不動産を、被相続人の子どもである相続人AとBの2人で分割する場面を例に挙げましょう。
「自宅不動産を相続人Aが、預金1,000円を相続人Bが相続する」という形で遺産分割協議がまとまれば、総額でみれば法定相続分どおりともいえます。
しかし厳密には、「相続人Aは預金500万円の権利を、相続人Bは自宅不動産の1/2の共有持ち分をそれぞれ失う」という約束事なのです。
このため相続人Aが単独名義で自宅不動産の所有権を登記しようとすれば、実印で押印された遺産分割協議書と印鑑証明書が必須とされるのです。
相続人全員の原本を作成
遺産分割協議書は、相続人全員分の原本を作成して、各相続人が保管するのが原則です。遺産分割協議を経て実際に財産を取得する際に、遺産分割協議書を提出しなければならないケースが少なくないからです。
前述した不動産の名義変更はもちろん、金融機関や証券会社の口座の名義変更などでも遺産分割協議書を提示しなければなりません。手続きをする方以外の相続人が、その財産の権利を失うことに合意している旨を示す必要があるからです。
仮に人数分の遺産分割協議書を作成しなければ、1人の相続人が遺産分割協議書を要する手続きを行っている間、他の相続人の手続きが滞ってしまいます。
遺産分割に関するよくある質問
遺産分割は、遺産の内容や相続人の関係などによって適切な方法がまったく異なる手続きです。
遺産分割に関する理解をより深めるため、よくある質問をチェックして、生じがちな疑問を解消しておきましょう。
借金があり遺産がマイナスの場合は?
被相続人のプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多く、実質的な遺産がマイナスの場合には、遺産分割は有効に作用しません。
仮に遺産分割で「相続人の1人がすべての責任を負う」と定めても、他の相続人が債務の返済から逃れることはできないからです。
借金を相続するリスクを回避する手段は、遺産分割ではなく、相続放棄もしくは限定承認の手続きです。いずれを選択する場合にも、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄(限定承認)の申述をしなければなりません。
被相続人に借金がある場合には、仮に遺産がマイナスにならなくとも注意が必要です。
前述したとおり、特定の相続人がすべての借金の責任を負う旨を遺産分割協議で定めても、あくまでもその内容は相続人同士の間の約束にしか過ぎません。債権者に対しては、法定相続分に応じた債務の返済義務を負わなければならないのです。
故人の介護をしていた人は遺産を多く受け取れる?
被相続人に対して献身的な介護をしていたなど、特別な貢献をしたと認められる相続人に遺産の配分を多くする「寄与分」という制度があります。
このような貢献を遺産分割に反映する仕組みといえますが、現実的にはトラブルになりがちな要素であることも事実です。
寄与分が認められるポイントは、被相続人の「財産の維持もしくは増加」に特別な貢献をしたという点です。つまり、いくら献身的に介護をしても、それによって財産の維持・増加につながらなかった場合には寄与分として認められません。
また、そもそも相続人と被相続人の間には「親族間の互助義務」という概念があります。これは民法730条に定められた「直系血族および同居の親族は、互いに扶け(たすけ)合わなければならない」という規定によるものです。
介護などを行うことは互助義務の範囲内と捉えられる可能性があり、通常想定される範囲を超えた貢献がなければ寄与分は認められません。
遺言書に書かれていない遺産はどうする?
遺言書に書かれている財産は遺言書に従って対応するのが原則ですが、遺言書に記載がない財産に関しては、遺言書がない場合と同様に扱われます。
つまり、相続開始時点で法定相続人全員の共有状態となり、遺産分割を行うことでそれを取得する相続人を決めるのです。
このため遺言書がある場合でも、すべてのケースで遺産分割が不要であるとは限りません。
遺産がいらない場合は?
遺産がいらない場合には、大きく分けて2つの方法が考えられます。1つは相続放棄で、もう1つは相続分の放棄です。遺産がいらないと考えた理由に応じて、取るべき方法が異なります。
相続放棄は、相続人の権利・義務を一切放棄する手続きで、もともと相続人ではなかったと扱われます。相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に対して申述し、認められなければ相続放棄はできません。
権利だけでなく義務も放棄する手続きですから、借金を相続する義務からも逃れられます。
例えば被相続人が資産と負債を残して亡くなった場合、「負債を解消する手続きの負担を考慮すると、遺産をもらわなくてもよい」と考える相続人がいても不思議はありません。このような場合には、相続放棄の手続きを取ることが適しています。
なぜなら相続財産に含まれる負債は、仮に遺産分割の中で「財産を受け取らない代わりに負債の責任を負わない」と合意したとしても、それを債権者に対して主張できないからです。
一方で、特定の相続人に財産を集めたい場合には相続分の放棄が適しています。相続放棄では相続人の権利・義務をすべて放棄しますが、相続分の放棄では相続人としての地位は維持し、権利だけを放棄できます。
被相続人の妻と2人の子どもが相続人となり、子ども2人が妻(子どもたちにとっての母親)に全財産を譲りたいと考えた場面を想定してみましょう。
このケースで2人の子どもが相続放棄をしても、妻がすべての遺産を受け取れるとは限りません。子どもが相続放棄をすれば、「配偶者と被相続人の親」「配偶者と被相続人の兄弟・姉妹」というように相続人が変わる可能性があるからです。
一方で、2人の子どもが相続分の放棄を行えば、相続人という立場を残したままプラスの財産だけを妻へと譲れます。
遺産分割はいつまでにやればよい?
遺産分割には、「いつまでにやらなければならない」といった明確な期限はありません。しかし遺産分割を行っていなければ、相続税の申告の際に税が軽減される特例が適用されないなどの支障が出る可能性が生じます。
このため、相続税の申告期限である相続開始から10カ月以内が1つの目安といえるでしょう。
ただし現実的には、遺産分割を終えなければ財産の活用ができないケースも多いため、できるだけ早めに行うのが基本です。
凍結された預金口座から現金をおろすにも、株式などの金融資産を売却するにも支障が出るからです。
遺産分割で専門家の力を借りたい場合
遺産分割を進めるうえで力を借りられる専門家には、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などがいます。
それぞれの専門分野が異なるため、遺産分割の支障になっている要因や、最も相談したい事柄に応じて選ぶことが大切です。
遺産分割を相談できる専門家は4士業
遺産分割を相談できる専門家は、弁護士・税理士・司法書士・行政書士の4士業です。
ただし、これらの士業の全員が相続を専門に扱っているとは限りません。いずれの専門家を選ぶにしても、第一に「相続を専門に扱っているか否か」を確認してから依頼することが必要です。
4士業の専門分野はそれぞれ異なりますが、相続を扱う士業は一般的に、専門分野ごとに連携体制を取っています。
仮に行政書士に遺産分割を依頼して相続税の申告が必要だとわかったとしたら、提携している税理士と連携してスムーズに業務を進めてもらえます。
もちろん相談したい内容に応じて専門家を選ぶことが解決の近道になりますから、後述する専門分野を踏まえて依頼先を検討すればよいでしょう。
弁護士に依頼する場合
弁護士に相続の相談を依頼すべき代表的なケースは、当事者間で遺産分割協議が合意に至らず、相続人同士でもめている場合です。その場合はむしろ、依頼先を弁護士にしぼったほうがよいでしょう。
当事者だけでの合意形成が難しく、調停などで解決の道を探る場合には、代理人として相続人の主張を代弁できるのが弁護士だけだからです。
遺産分割調停や審判の場では、調停委員会に対して、相続人の主張を法に則して合理的に説明しなければなりません。
法律の知識に明るくなければ難しい手続きのため、弁護士に依頼することでご自身にとって有利な結論を引き出せる可能性が高まります。
一方で、弁護士は依頼人の利益のために業務を行う専門家ですから、仲裁役ではないことを頭に入れておかなければなりません。
税理士に依頼する場合
相続手続きにおける税理士の専門業務は相続税の申告です。このため、相続財産の評価に関してもアドバンテージを持つ専門家といえます。
不動産や非上場会社の株式など、評価額の算出が難しい財産が含まれる場合には、遺産分割を税理士に依頼することで円滑に進む可能性が高くなるのです。
逆の言い方をすれば、相続税申告の必要がなく、遺産の中に財産評価が難しいものが含まれないケースでは、他の専門家を選択するほうが有効に作用する可能性があり得ます。
司法書士に依頼する場合
司法書士に遺産分割を相談すべき場面は、遺産の中に不動産が含まれ、その所有権移転登記(名義変更)を依頼したいときです。
遺産分割協議を経て不動産を取得した相続人は、その根拠が示された遺産分割協議書を添付して登記申請をしなければなりません。
単純に法定相続分どおりに共有登記をするのであれば、相続登記は容易に行えます。遺産分割協議書も必要なく、共同相続人の1人による単独での申請もできるのです。
しかし、遺産分割で特定の相続人が不動産を取得する場合は、他の相続人が法定相続分に応じた所有権を手放すことを意味しています。
このように「誰かに不利益が生じる恐れがある登記」には、より厳格な手続きが必要とされるため、登記の専門家である司法書士に依頼するのが有効といえるのです。
行政書士に依頼する場合
行政書士は「権利関係を示す法的書類の作成」の専門家です。このため遺産分割を依頼するケースでは、トラブルの懸念がなく遺産分割協議書の作成だけを依頼したい場合などが適任といえます。
「他の業務に付随して遺産分割協議書を作成する」という立場の他士業と異なり、行政書士はそれだけを依頼できる専門家です。このため遺産分割協議書の費用の面でも有利になる可能性があります。
行政書士に遺産分割を相談すべきなのは、相続税申告や不動産登記の必要がない場合のほか、遺産に農地が含まれるなど特定の行政手続きが必要な場合です。
相続財産の中には、当事者間だけでは権利のやり取りができないものが存在します。農地が含まれるケースでは、農業委員会に対して届け出をしなければならず、換価分割などを選択しようとした場合には、さらに要件の厳しい「許可」という手続きが必要です。
このような特定の遺産が含まれるケースでは、行政書士に遺産分割を依頼するとよいでしょう。
トラブルの懸念がある場合は弁護士へ
当事者同士での話し合いが難しいと感じる遺産分割や、相続財産に借金があり債権者の対応が必要になる場合など、何らかのトラブルに発展する懸念があるときには弁護士に依頼するのが最善の選択といえます。
すべての相続の場面で、円滑に遺産分割が進むとは限りません。生前贈与や寄与分など捉え方によっては、「ご自身が受け取る権利のある遺産額」に関する考えが相続人ごとに異なるケースも少なくありません。
また、相続財産に借金が含まれるものの、遺産の総額がマイナスにならないことから相続放棄を選択しなかったような場合にも注意が必要です。
法律上、相続財産に含まれる債務は当然に法定相続分に応じて分割されることとされています。つまり、遺産分割協議によって法定相続分とは異なる分割割合を選択しても、債権者の合意を得なければそれを主張することはできないのです。
このようにトラブルの懸念がある場合は、依頼人の利益のために代理業務を行える弁護士へ依頼するのが適切です。
おすすめの記事
ほかにもこちらのメディアでは、遺産分割協議書は自分で作成できるかどうかや遺産分割協議書が作成できる必要書類についても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。