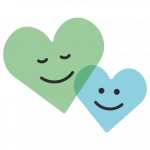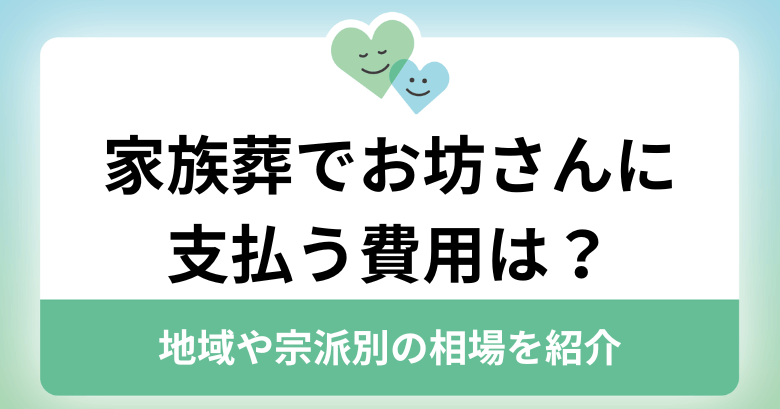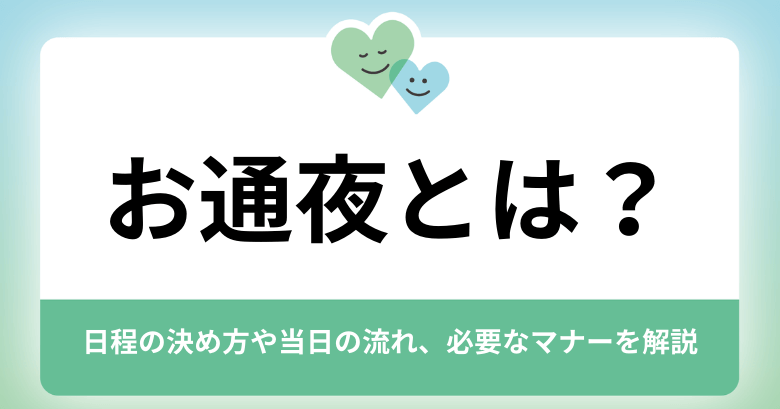
※当記事はPRを含みます。
お通夜の基礎知識を身に付けたいと考えていませんか?
お通夜を円滑に執り行うためには、お通夜の概要や日程の決め方、流れなどを知ることが大切です。
本記事では、仏教の考え方を基本として、お通夜に必要な情報をまとめました。服装や香典に関するマナーも解説するため、ぜひ最後までご覧ください。
- お通夜とは、遺族と参列者が故人を偲ぶための儀式
- お通夜の一般的な流れは、受付・記帳、読経、焼香、通夜振る舞いである
- お通夜では、服装、持ち物、香典、言葉遣いに気を付ける
お通夜とは親しい方と故人を偲ぶ儀式
お通夜とは、親族や友人などの故人と親しい方々が集まり、故人を偲ぶための儀式です。
偲ぶ(しのぶ)という言葉には、「遠く思いをはせて、なつかしがる」という意味があります。したがって、「遺族と親しい方々で、故人との思い出をなつかしむ儀式」と言い換えてもよいでしょう。
日程と参列者
お通夜は、ご本人が亡くなった日の晩または翌日の晩に執り行われます。仮に当日の午後に亡くなった場合、以下のようなスケジュールとなるでしょう。
| 1日目 | お亡くなりになった当日 |
|---|---|
| 2日目の18時頃から開始 | お通夜 |
| 3日目の10時頃から開始 | 告別式・火葬 |
葬儀の日程に明確な取り決めはありません。しかし、ご遺体を適切に維持する、参列者の予定に配慮するといった理由から、すみやかに準備に取りかかることをおすすめします。日程を決める際の注意点は後述します。
お通夜の参列者を決めるのは遺族です。故人の意向や故人との関係性を重視して、最終的に遺族がお招きする方を決めます。「参列者の範囲がわからない」という方は、以下の基準を参考にしましょう。
- 直系の親族(3親等まで)
- 配偶者の親族(3親等まで)
- 故人との交流が深い友人・知人
- 仕事でお世話になった方
3親等の親族とは、こちらの方々を指します。
- 子、孫、ひ孫、甥・姪
- 父母、伯父・叔母、祖父母、曽祖父母
なお、「〇〇さんを必ず呼んでほしい(呼ばないでほしい)」と、故人が遺言を残すケースもあるでしょう。この場合の遺言は付記事項に該当するため、法的拘束力はないと考えられています。お通夜の規模に合わせて、遺族が参列者を決めても問題はありません。
告別式・葬式との違い
お通夜は、親しい方々と故人を偲ぶための儀式です。一方の告別式は、故人との最期のお別れを行う儀式を指します。つまり、遺族や参列者は、お通夜によって故人を偲び、告別式を通じて故人とお別れをするわけです。
葬式・葬儀は、「葬送儀礼」の略称で、故人の冥福を祈り死者を葬るための儀式全般を指します。臨終を迎える方の看取り、お通夜、告別式、火葬などの一連の儀式や作業も葬式・葬儀に含まれます。
本通夜と仮通夜の違い
仮通夜とは、ご本人が亡くなった当日に、故人と親族だけで行われる通夜のことです。親族が故人を見守り、静かに一晩過ごすことを目的としています。自宅で執り行われるため、参列者を伴わない点も特徴の1つです。
友人・知人、お世話になった方が参列する通夜は「本通夜」と呼ばれ、仮通夜とは区別されています。
仮通夜は本通夜の前日に行われます。亡くなった当日に本通夜を執り行う際は、仮通夜は行えませんのでご注意ください。
お通夜の日程を決める際の注意点
お通夜の日程を決める際は、どのような点に注意すべきでしょうか?具体的な項目を解説します。
家族葬ではお通夜を省く場合もある
家族葬とは、身内などの親族を中心に行う葬儀の形式です。少人数で、静かに故人をお見送りしたいという希望を叶える方法の1つとなります。
家族葬に明確な定義はなく、参列者をお招きしても構いません。参列者を招かない場合は、お通夜を省略することが可能です。
少子高齢化に伴い、出席する親族の体力的負担も問題となっています。そのため、お通夜を省略して葬式、告別式を行う遺族も増えているようです。お通夜を省略して、葬式・告別式からはじめる形態を「一日葬」と呼びます。
友引を避ける
六曜における友引(ともびき)にも注意が必要です。六曜とは、中国で生まれ日本に伝わった吉凶を占う暦の1つです。友引は「友を引く」と書くため、葬式の際に避ける風習があります。
もしも友引にお通夜を執り行うと、親族や参列者の中から不安を覚える方が出てくるかもしれません。
しかし、仏教と六曜との間に明確な関係性はなく、友引にお通夜を行っても間違いではありません。親族や参列者との間で問題がなければ、友引にお通夜を執り行ってもよいとされています。
火葬場の空き状況を確認する
お通夜は葬儀・告別式の前日に執り行われます。火葬場の空き状況を確認してからお通夜の開催日を決めると、滞りなく葬儀が進行するでしょう。
火葬場の手配は、葬儀社に依頼するのがおすすめです。なぜなら、火葬するまでには、死亡届や火葬許可申請書を自治体に提出する、ご遺体に適切な処置を施すといった必要かつ大変な手続きがあるからです。
故人がお亡くなりになったあとで、そうした作業は心身に負担をかけます。無理をせず葬儀社に依頼しましょう。
なお、日本では葬儀を終えた後、故人の遺体が火葬されます。土葬も法律上は可能ですが、条例などにより禁止されている市町村が少なくありません。そのため遺族の多くは、火葬を選択しているようです。
僧侶や菩提寺に連絡する
お通夜では僧侶が読経して参列者が焼香する方式をとるため、僧侶の手配が欠かせません。菩提寺がある場合は、菩提寺(ぼだいじ)へ連絡して、僧侶を手配しましょう。
菩提寺とは、先祖代々のお墓があり長年供養してもらっているお寺のことです。葬儀の日程や場所についても相談にのってもらえるでしょう。菩提寺に連絡せず僧侶を手配すると、後々のトラブルにつながるため、必ず菩提寺に連絡を入れましょう。
菩提寺がない場合は、葬儀社を探して依頼するほか、お寺に直接問い合わせをする方法があります。
遺族や参列者に配慮する
お通夜の日程を決める際は、遺族や参列者の予定にも配慮できるとよいでしょう。招きたい方がいれば、できるだけ早く連絡を入れます。
故人の近親者、お世話になった方に無理のない日程で開催できるのが理想的です。しかし、お通夜を滞りなく進行させるためには、火葬場の空き状況や僧侶の予定が優先されます。無理のないスケジュールを意識してみてください。
お通夜当日の流れと確認事項
お通夜当日の流れについて、主に参列者の目線から5つの段階に分けて解説します。
- 受付・記帳
- 僧侶による読経
- 焼香
- 通夜振る舞い
- 閉式
それぞれの意味や注意点をみていきましょう。
1.受付・記帳
はじめにお通夜の会場で、受付と記帳を済ませます。受付に、「この度はご愁傷様です」または「お悔やみ申し上げます」とお悔やみの言葉を伝えてから、芳名帳(ほうめいちょう)にご自身の氏名や住所を記入します。
芳名帳の記録は、後ほど香典返しを送る際に活用されるため、住所は枝番まで詳しく記載しましょう。芳名カードが手元にある場合は、芳名カードに氏名や住所を記入してお渡しします。
会社の人間として記帳する場合は、以下の点にご注意ください。
- 会社名、所在地、所属部署を記入する
- ご自身の氏名・住所は会社名のあとに記入する
受付・記帳を済ませた後に、袱紗(ふくさ)から香典を出してお渡しします。相手からみて、表書きが読める向きに変えてからお渡ししましょう。
なお、一般的な受付開始時間は、開始時刻の30分から1時間前となります。18時開始の場合は、17時頃から受付できるはずです。参列する際は天候や道路の込み具合などを確認して、余裕を持った行動を心がけましょう。
2.僧侶による読経
受付後は、会場の席に座り開式を待ちます。定刻になると司会者より開式の挨拶があり、間もなく僧侶による読経がはじまります。
読経とは、故人の供養のために読み上げるお経です。読経は、参列者に対しても功徳やご利益があると考えられているため、耳を傾けるとよいでしょう。
3.焼香
続いて焼香がはじまります。焼香とは、香を焚いて、故人や仏に対して拝む行為のことです。また、邪気を払って体を清めるという意味もあります。
種類と特徴
焼香の回数や作法は、宗派によって異なります。葬儀の席では、故人の宗派に合わせてもご自身の宗派に合わせてもどちらの作法を選んでも問題ありません。
| 種類 | 方法 | 会場 |
|---|---|---|
| 立礼焼香 | 祭壇前の焼香台にて立って行う | 広い会場 |
| 座礼焼香 | 祭壇前の焼香台にて正座して行う | 小規模な会場 |
| 回し焼香 | 香炉と抹香を回して行う | より狭い会場 |
順番とやり方
焼香の順番は、血縁に基づいて行われます。一般的な順番を確認しましょう。
- 喪主
- 遺族
- 親族
- 故人の親しい友人・知人
続いて、焼香のやり方をみていきましょう。
- 焼香台の手前でとまる
- 遺族と僧侶にそれぞれ一礼する
- 焼香台の前に進み、正面に向かって一礼する
- 右手の親指、人差し指、中指の3本で抹香をつまむ
- 額に近づけてから香炉にくべる
- 焼香台から数歩下がり、一礼する
- 僧侶、遺族に一礼してから、ご自身の席へ戻る
焼香が終わる頃に、僧侶による法話が行われます。法話とは、仏教の教えに基づいた話を、僧侶が一般の方が理解しやすいように説き聞かせることです。リラックスして耳を傾けましょう。
法話が終わり僧侶が退場したあとは、喪主よりお通夜閉式の挨拶があります。告別式の時間や場所、通夜振る舞いの案内がありますのでご注意ください。
4.通夜振る舞い
通夜振る舞いとは、僧侶や参列者を招いて行われる食事会のことです。僧侶や参列者に食事を振る舞うことで、遺族が感謝の気持ちを表します。また、食事の席で故人の思い出話などをして、故人を偲ぶことも大切な目的です。近年の通夜振る舞いは、1時間から2時間ほどで終了となるケースが増えています。
通夜振る舞いには、残された遺族の心をなぐさめるという意味もあります。出席は強制ではありませんが、招かれた場合は極力参加しましょう。通夜振る舞いでは、お箸をつけることが供養になると考えられているため、一口でもいただくことが大切です。
通夜振る舞いの開式・閉式の挨拶は、喪主から行われます。もしも式の途中で退席する場合は、遺族に一言伝えてから退席しましょう。
5.閉式
通夜振る舞いの閉式をもって、お通夜は終了となります。ここで帰宅する際に、お通夜の会場で「清めの塩」をいただく場合があります。
清めの塩とは、人の死に寄ってくる邪気を穢れ(けがれ)として捉え、塩によって穢れを払い身を清める方法です。一般的なやり方は以下のとおりです。
- 胸、背中、足元の順番で塩をふりかける
- 残った塩を手で払う
- 手で払った塩を踏んでから玄関にはいる
清めの塩は、自宅の玄関をまたぐ前に行いますのでご注意ください。
お通夜のマナーとは
お通夜には、服装や言葉遣いに関するマナーが存在します。遺族や参列者に失礼のないよう、以下の項目を確認しましょう。
服装
お通夜では喪服を着用します。喪服とは、葬儀や法事などの弔事で着用する服のことで、以下の3種類が存在します。
| 種類 | 着用者 | 特徴 |
|---|---|---|
| 正喪服 | 〇遺族 ×参列者 | 最も格式の高い喪服 (和装、モーニング) |
| 準喪服 | 〇遺族 〇参列者 | 一般的な喪服 (ブラックスーツ、ワンピースなど) |
| 略喪服(平服) | ×遺族 〇参列者 | 急遽駆けつける場合の喪服 (ブラックフォーマル以外のダークスーツ、ワンピースなど) |
お通夜では、参列者が遺族より格式の高い喪服を着用しないのがマナーです。そのため参列者は、準喪服または略喪服を着用します。遺族の場合は、正喪服または準喪服を着用します。
男性の場合
男性の場合は、光沢や艶がない黒のブラックスーツを着用しましょう。喪主・遺族が和装を着用する場合は、葬儀社のレンタルを利用するのもおすすめです。
ブラックスーツの場合は、白色で無地のワイシャツを選び、ベルトやネクタイピンに金色の付属や派手な柄を選ばないようご注意ください。エナメル素材の靴も避けましょう。
女性の場合
女性の場合は、長袖で光沢のないワンピースまたはブラックスーツを着用します。肌の露出を避ける必要があるため、透け感のある喪服は避けて、スカートはひざが隠れるくらいの丈を意識しましょう。
細かい注意事項を以下の表にまとめました。
| 注意点 | |
|---|---|
| メイク | 基本はナチュラルメイク 派手なメイクやノーメイクはNG |
| 髪型 | ゴム・ピンを使って低めの位置でまとめる 華やかな印象はNG |
| マニキュア | 透明・落ち着いた色を選ぶ 黒の手袋を着用してもよい |
喪服がない子どもの場合
子どもの喪服がない場合は、制服を着用します。幼稚園や学校指定の制服を着用して問題ありません。
制服がない場合は、黒、グレー、紺などのダークカラーの上着とスカート・ズボンを着用し、白いシャツやブラウスを合わせましょう。光沢のある素材やデニム素材は避けます。
持ち物
お通夜の席では、持ち物にも配慮が必要です。訃報に心を痛めているご遺族に、不快な思いをあたえない持ち物を選びましょう。
具体的には、派手な色合いを避け、黒やグレーを選びます。金属部分が金色になっているものや光沢のある素材にご注意ください。
アクセサリー・ハンカチ
結婚指輪以外のアクセサリーは外しておきます。女性がネックレスを身につける際は、一連のパールのネックレスを装着しましょう。2連や3連のネックレスを着用すると、「不幸が重なること」を連想させてしまうからです。
ハンカチに関しては柄物や派手な色を避け、無地で白色のものを選ぶのがマナーです。タオル素材のハンカチには色柄がついていますので、綿素材を選びましょう。
鞄
男性の場合は、鞄を持ち込まず手ぶらで参列するのがよいでしょう。お通夜の前後に予定が入っているため手荷物がある場合は、近くのコインロッカーなどに預け、会場に向かうことをおすすめします。
女性の場合は、ショルダーバッグなどのカジュアルな形態、光沢のある素材を避けるのがマナーです。また、「殺めること」を連想させるため、動物の革を使った製品も避けましょう。
香典
香典とは、故人を偲ぶ気持ちを表すために、霊前にお供えする金品のことです。お花やお香の代わりに故人の霊前に添えます。お通夜では遺族に急な出費が発生しますので、金銭的に遺族を助けるという意味合いも含まれています。
香典袋に薄墨の毛筆を使用して表書きを記入した後、必ず袱紗に入れて持参しましょう。表書きの記入例がこちらです。
| 表書き | |
|---|---|
| 仏教 | ご霊前 ご仏前 |
| 神道 | 御榊料(おさかきりょう) 御玉串料(おたまぐしりょう) |
| キリスト教 | 御花料 献花料 |
なお、香典にお札を入れる際は、新札を使わないようご注意ください。新札を使用すると、「お通夜のために用意しておいた」と不謹慎に捉えられるおそれがあるからです。
お通夜は突然の不幸を悼む場であるため、旧札を使用するのがマナーとなります。どうしても新札しか用意できない場合は、折り目をつけてから使用しましょう。
香典の相場は、故人との関係が深いほど高くなります。一般的な相場がこちらです。
| 故人との関係 | 一般的な相場 |
|---|---|
| 両親 | 5万円から10万円 |
| 兄弟・姉妹 | 3万円から5万円 |
| それ以外の親戚 | 1万円から3万円 |
| 友人・知人 | 5,000円から1万円 |
| 会社関係の同僚など | 5,000円から1万円 |
言葉遣い
お通夜では、忌み言葉と重ね言葉を使用してはいけません。
忌み言葉とは、不吉な意味を連想させる言葉を指し、お通夜を含む葬儀の席では使用を控えます。重ね言葉とは、同じ意味の言葉を重ねた表現のことで、重言とも呼ばれます。不幸が重なることを連想させるため、忌み言葉と同様に葬儀では使用しません。
具体例がこちらです。
| 忌み言葉 | 死 死ぬ 死亡 散る 消える 悲運 災厄 終わる |
|---|---|
| 重ね言葉 | またまた 次々 重ね重ね いよいよ |
忌み言葉や重ね言葉だけでなく、故人の亡くなった原因を尋ねたり大きな声で話したりすることも避けましょう。
お通夜では、遺族の気持ちに配慮した立ち振る舞いが大切です。
事情があって参列できないときは
何らかの事情によって、定刻に参列できないときは、喪主または遺族に遅れる旨の連絡を入れましょう。連絡ができない場合は、受付に連絡します。
お通夜の場に到着したあとは、まず受付に向かいます。遅れたことへのお詫びを伝えてから、お焼香したい旨を伝えましょう。香典を受け付けているようであれば、その場でお渡しして構いません。
喪主や遺族とお会いできたら、まずお悔やみの言葉を伝えてから、遅れたことへのお詫びを伝えます。香典を受付でお渡しできなかった場合は、直接喪主にお渡しするのもよいでしょう。
なお、どうしても参列できない場合は欠席の連絡を入れます。その際は、供物・供花を送る他、弔電によってお悔やみの気持ちを伝えましょう。
おすすめの記事
ほかにもこちらのメディアでは、通夜と告別式の違いについてや香典とは何かについても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。