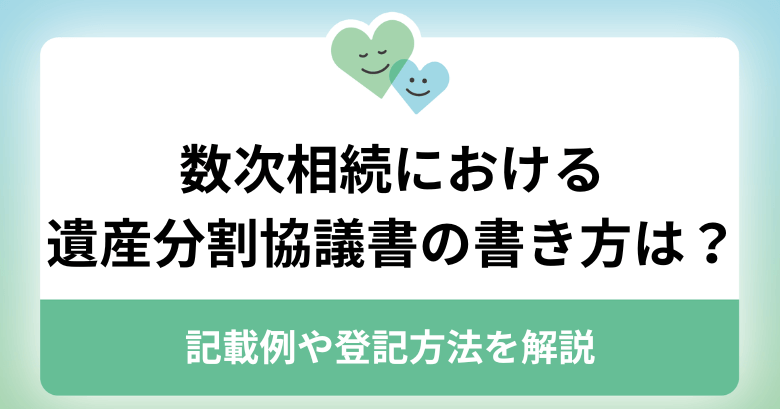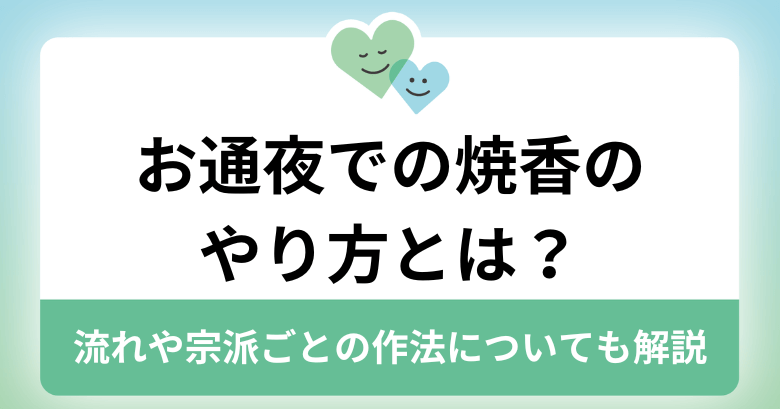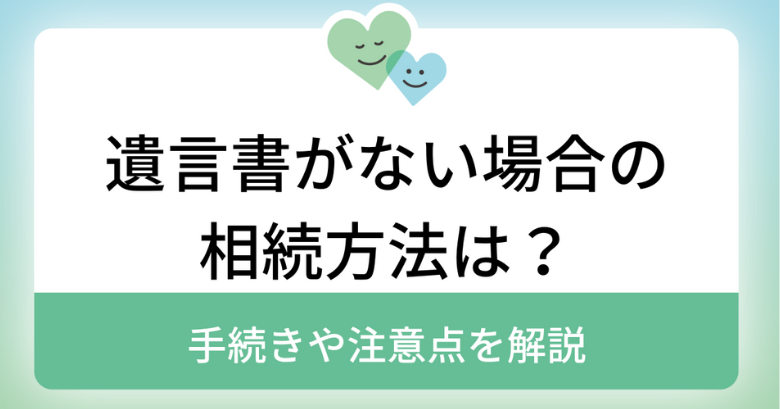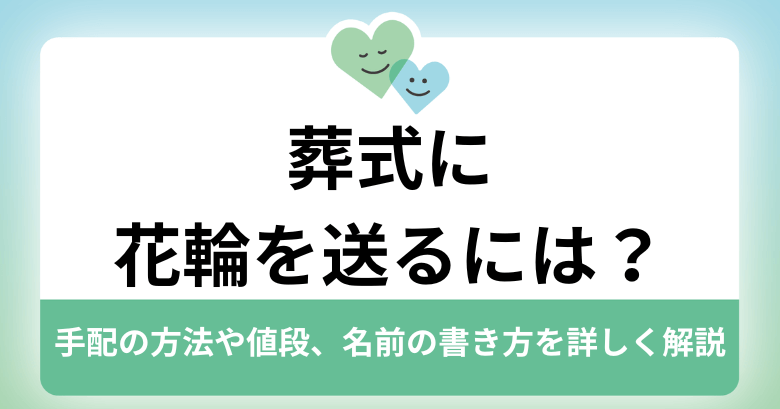※当記事はPRを含みます。
遺産分割調停で問題になるのが「どこに申立てるか」です。
調停を申立てる裁判所は、基本的には相手方が実際に住んでいる場所を管轄する家庭裁判所と決まっています。しかし、条件を満たせば裁判所を好きに選択したり、管轄以外の裁判所で調停手続きをしたりできます。
この記事では、調停を申立てる裁判所や調停でも話がまとまらない場合について解説します。また、調停への参加が難しい場合の対処法についても解説しているため、ぜひ参考にしてください。
- 遺産分割調停は、相手方が実際に住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に申立てる
- 相手方が複数名いる場合は管轄裁判所を選択でき、すべての相続人が合意がすれば管轄以外でも申立て可能
- 調停でもまとまらない場合は審判に移行する
遺産分割調停とは
遺産分割調停とは手続きの一つで、遺産をどのように分割するかを話し合う「遺産分割協議」がまとまらなかったときに行われます。
また、遺産分協議に協力してくれない相続人がいる場合や、連絡がつかない相続人がいる場合などにも利用されます。
調停の際は調停委員が間に入って話し合うため、当事者は直接顔を合わせる必要がなく、遺産分割協議の場ではお互いに感情的になっていたケースでも冷静な話し合いができる可能性があります。
なお、調停は相続人の1人、または何名かが連名でほかの相続人を相手方として管轄の裁判所に申立てます。
遺産分割調停の管轄裁判所はどこ?
遺産分割調停の申立て先はどこの裁判所でもよいというわけではなく、申立てるべき裁判所が決まっています。ここでは、調停を申立てる裁判所について解説します。
基本的には相手方が実際に住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に申立てる
遺産分割調停は、基本的には相手方が実際に住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に対して申立てます。家事事件手続法第245条第1項でそのように定められているためです。
たとえば申立人が東京都、相手方が愛知県に居住している場合は、名古屋家庭裁判所に対して調停を申立てなければなりません。
ただし条文に記載があるように、家事事件手続法第245条第1項では、当事者が合意で定める裁判所についても認めています。なお、当事者が合意で定める裁判所については後述します。
遺産分割調停やその流れについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
相手方が複数名いる場合は管轄裁判所を選択できる
相手方が複数名存在する場合は、それぞれが実際に住んでいる場所を管轄する裁判所の中から、申立人が自由に選べます。
事例で見てみましょう。
| 実際に住んでいる場所 | 管轄裁判所 | |
|---|---|---|
| 申立人 | 千葉県千葉市 | – |
| 相手方A | 東京都 | 東京家庭裁判所 |
| 相手方B | 大阪府大阪市 | 大阪家庭裁判所 |
| 相手方C | 福岡県福岡市 | 福岡家庭裁判所 |
以上のケースでは、東京、大阪、福岡の3つの家庭裁判所の中から選べます。申立人が居住している場所からもっとも近い東京家庭裁判所を選べば、申立人は裁判所に出向きやすく交通費も抑えられます。
管轄裁判所は裁判所のサイトで検索が可能
管轄裁判所は裁判所の公式サイトから検索できます。トップページ以降の手順は以下のとおりです。
- 裁判手続案内
- 裁判手続を利用する方へ
- 裁判所の管轄区域
「裁判所の管轄区域」を開いたら、管轄裁判所を調べたい都道府県をクリックし、管轄区域一覧の「地方・家庭裁判所」を見ます。その際、家裁出張所欄・支部欄に記載があるかどうかで管轄裁判所が決まります。
| 記載の有無 | 管轄裁判所 |
|---|---|
| 家裁出張所欄に記載がある場合 | その家裁出張所 |
| 家裁出張所欄に記載がなく支部欄に記載がある場合 | その支部 |
| 家裁出張所欄にも支部欄にも記載がない場合 | 本庁 |
たとえば東京都千代田区の場合、家裁出張所欄にも支部欄にも記載がないため、本庁である「東京地方・家庭裁判所」が管轄裁判所です。
遺産分割調停を管轄以外の裁判所でできるケースもある
管轄以外の裁判所に調停を申立てられるケースもあります。ここでは、管轄以外の裁判所で調停ができる2つのケースについて解説します。
相続人全員の合意があれば管轄外での調停が可能
遺産分割調停は、すべての相続人が合意しているならば管轄以外の裁判所でも行えます。相続人の合意によって管轄裁判所を自由に決めることを「合意管轄」といい、相続人がそれぞれ離れた場所に居住している場合に有効な制度です。
合意管轄裁判所は、たとえば以下のように定められます。
- それぞれの相続人が居住している場所の中間地点に位置する裁判所で調停を行う
- 被相続人が最後に居住していた場所を管轄する裁判所で調停を行う
合意管轄が認められるためには、すべての相続人が合意したことを証明する書類「管轄合意書」を裁判所に提出する必要があります。
管轄合意書はそれほど複雑な書類ではないため、ご自身でも作成が可能です。どの裁判所を合意管轄裁判所とするかを記載した書面を作成し、提出すれば問題ありません。書面には作成日を記載し、相続人全員が署名・押印します。
特別な事情が認められた場合は「自庁処理」が可能
自庁処理とは、管轄以外の裁判所が、事件を処理するためにとくに必要と判断した場合に職権で処理を進めることです。
通常であれば、管轄以外の裁判所に対して調停を申立てた場合、申立てを受けた裁判所は本来の管轄である裁判所に申立てを移送します。しかし裁判所がとくに必要であると認めた場合は、申立人の最寄りの裁判所で調停ができる可能性があります。
とはいえ、どのような理由でも認められるわけではありません。とくに必要がないと判断されれば自庁処理は認められず、申立ては通常どおり本来の管轄である裁判所に移送されてしまいます。
自庁処理が認められるためには、たとえば以下のような理由が必要です。
- 幼い子どもを預けられる人がいない
- 介護や看病のため長時間の外出ができない
- 金銭的な理由から遠方へ行くための交通費が捻出できない
- 心身の病気やけがなどが原因で遠出が困難である
なお、家事事件手続規則では、自庁処理による裁判を行う場合、当事者および利害関係参加人の意見を聴かなければならないとされています。
遠方で遺産分割調停への参加が難しい場合の対処法
すべての相続人の合意があれば好きに管轄裁判所を選べることや、特別な事情があれば管轄の裁判所以外でも調停ができる可能性があることについて前述しましたが、それでも調停への参加が困難な場合もあるでしょう。
相続人全員の合意が得られなかったり、自庁処理が認められなかったりすることもあるためです。しかし、そのようなケースでも対処法はあります。
ここでは、遺産分割調停への参加が難しい場合の対処法を紹介します。
電話会議システムを活用する
電話会議システムとは、電話で調停手続きを進める方法です。さすがに自宅や任意の場所からというわけにはいきませんが、最寄りの裁判所まで出向けば、管轄裁判所と電話での話し合いが可能です。
また、弁護士に依頼している場合は、弁護士事務所からでも電話会議システムが利用できます。そのため、わざわざ遠方の管轄裁判所まで出頭する必要はありません。
ただし、電話会議システムがどのようなケースでも利用できるわけではないため注意が必要です。
電話会議システムを利用しなければならない理由を裁判所に伝え、認めてもらえなければ利用できません。裁判所によっては、電話会議システム自体が利用できないこともあります。
電話会議システムを希望する場合は、事前に裁判所に問い合わせておいたほうがよいでしょう。
代理人に出席してもらう
遠方で遺産分割調停への出席が難しい場合、代理人を立てて代わりに出席してもらうのもひとつです。
家庭裁判所の許可が得られれば、例外的に家族や友人でも代理人として遺産分割調停に出席できますが、代理人を立てることを考えているのであれば弁護士に依頼するのがよいでしょう。
なぜなら、家族や友人が遺産分割調停に出席することについて家庭裁判所の許可を得たとしても、取り消されるケースがあるためです。
また、はじめは家族や友人でも十分対応できると思っていても、実際に調停や審判といった法的な場面に直面するうちに、やはり素人では対応が難しいのではと感じるかもしれません。
その点弁護士であれば、法的なルールに精通しているため安心して任せられます。ただし、当然ながら弁護士に依頼した場合は費用が発生します。そのため、総合的に考えて誰を代理人にするかを考える必要があるでしょう。
調停条項案に合意する内容の書面を提出する
遠方で遺産分割調停への参加が難しく、電話会議システムなども利用できない場合でも、調停条項案に合意する内容の書面を提出すれば調停を成立させられます。
家事事件手続法第270条では、以下のように定められています。
当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められている場合において、その当事者があらかじめ調停委員会(裁判官のみで家事調停の手続きを行う場合にあっては、その裁判官。次条及び第二百七十二条第一項において同じ。)から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が家事調停の手続きの期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなす
引用元:衆議院
つまり、以下の条件を満たせば、遺産分割調停に参加できなくても調停を成立させられるのです。
- 遺産分割調停への参加が難しい正当な理由がある
- 調停条項案に合意する内容の書面をあらかじめ提出している
- ほかの相続人が調停の期日に出頭し、調停条項案に受諾する
ただし注意しなければならないのは、調停条項案に合意できない場合や、ほかの相続人と意見が対立しているような場合です。
あくまでも、遺産分割調停の内容に異論がない場合や、とくに意見することがないような場合に利用できる方法であることを念頭に置いておきましょう。
遺産分割調停を行わずに遺産分割審判を申立てる
遺産分割調停を行わず、すぐに遺産分割審判を申立てるという手段もあります。遺産分割審判とは、相続人同士の話し合いによるものではなく、相続人それぞれの言い分や資料をもとに、家庭裁判所がどのように遺産を分割するかを決定する手続きです。
一般的には遺産分割調停でもまとまらない場合に遺産分割審判に移行しますが、必ずしも遺産分割調停を行ったあとでなければ遺産分割審判の申立てができないわけではありません。
遺産分割審判と遺産分割調停では管轄裁判所が異なるため、遺産分割審判の管轄裁判所のほうがよければ、遺産分割調停を申立てずに遺産分割審判を申立てても構わないのです。
ただし、遺産分割調停を経ずに遺産分割審判を申立てた場合、まずは遺産分割調停を申立てるよう家庭裁判所から指導を受ける可能性があります。その場合は、遺産分割調停を経てからでないと遺産分割審判はできません。
遺産分割調停でもまとまらない場合はどうなる?
遺産分割調停を経ても、話がまとまらないケースもあります。調停委員が間に入ってくれるとはいえ、結局は相続人同士での話し合いであり、1人でも納得できない人がいる場合は調停が成立しないためです。
お互い譲る気がない場合や関係がこじれてしまっている場合は、遺産分割調停をもってしても平行線のまま決着がつかないということも珍しくありません。
ここでは、遺産分割調停でも話がまとまらない場合について解説します。
遺産分割調停でもまとまらない場合は審判に移行する
遺産分割調停でも話がまとまらず不調に終わった場合、自動的に遺産分割審判に移行します。
前述のとおり、遺産分割審判は相続人同士での話し合いではなく、家庭裁判所が相続人それぞれの言い分を聞き、さまざまな資料や証拠を確認したうえで遺産をどのように分けるかを判断する手続きです。
審判はその場で口頭によって下されるのではなく、書面によって下されます。審判の結果を記した審判書は、審判終了後1〜2か月後にそれぞれの自宅に届けられます。
下された審判は強い強制力を持っており、内容に不服があったとしても覆せません。
遺産分割審判の管轄裁判所はどこ?
遺産分割審判の管轄裁判所は、遺産分割調停の申立て先とは異なる場合があります。また、以下の2つのケースのうち、どちらに該当するかによっても異なる可能性があります。
- 遺産分割調停から審判に移行した場合
- 遺産分割調停を経ずに審判を申立てる場合
それぞれケース別に解説します。
遺産分調停から審判に移行した場合
遺産分割審判の管轄裁判所は、原則被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。調停の管轄裁判所と、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所が同じ場合、変更はありません。
ただし、調停の管轄裁判所と被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所が異なる場合でも、調停がまとまらず審判に移行した際は、調停の管轄裁判所となった裁判所がそのまま審判も行うケースがあります。
調停を行った裁判所が審判も引き継ぐかどうかは事件別に判断されるため、調停から移行したからといって、必ずしも同じ裁判所が管轄裁判所になるとはかぎらない点には注意が必要です。
なお、調停の場合と同様に、相続人全員の合意があれば被相続人の最後の住所地以外の裁判所への申立ても可能です。
遺産分割調停を経ずに審判を申立てる場合
遺産分割調停を行わず、はじめから遺産分割審判を申立てる場合の管轄裁判所は、被相続人が最後に居住していた場所を管轄する家庭裁判所です。
たとえば、東京都に住んでいた被相続人がそのまま東京都で亡くなった場合、相続人が誰1人東京に住んでいなくても、遺産分割審判は東京家庭裁判所に申立てる必要があります。
遺産分割調停から遺産分割審判に移行した場合とは異なり、相続人全員の同意があったとしても、合意管轄は利用できません。
まとめ
遺産分割調停の管轄裁判所や、遠方で遺産分割調停に参加できないときの対処法、遺産分割調停を申立てても話し合いがまとまらない場合について解説しました。
遺産を誰がどのように相続するかは、どうしても争いが起きやすい問題です。そのため、遺産分割調停に発展するケースは珍しくありません。
また、長引くケースも少なくないため、管轄裁判所が遠方であればあるほど体力・気力ともにすり減ってしまいます。少しでも負担なく遺産分割調停を進めたい人は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
ほかにもこちらのメディアでは、遺産分割協議書の提出先や遺産分割協議の期限についても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。

-e1693177449149.jpeg)