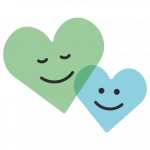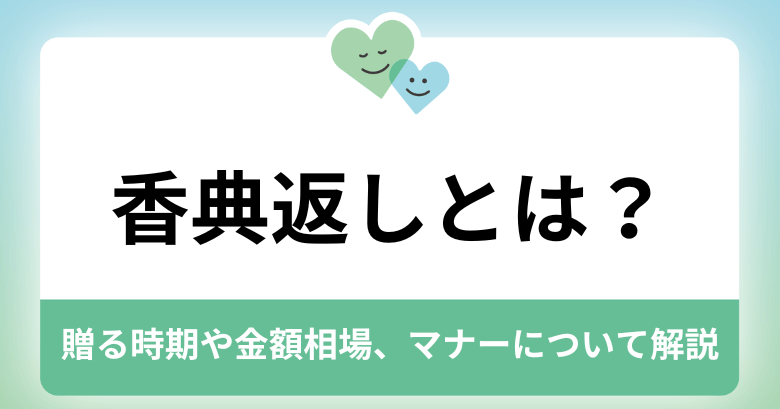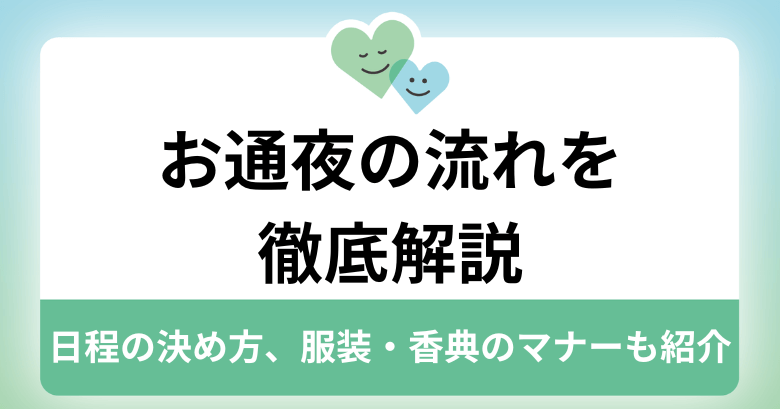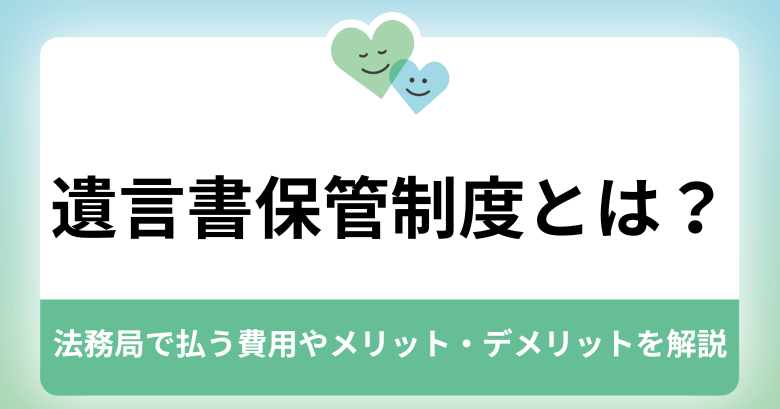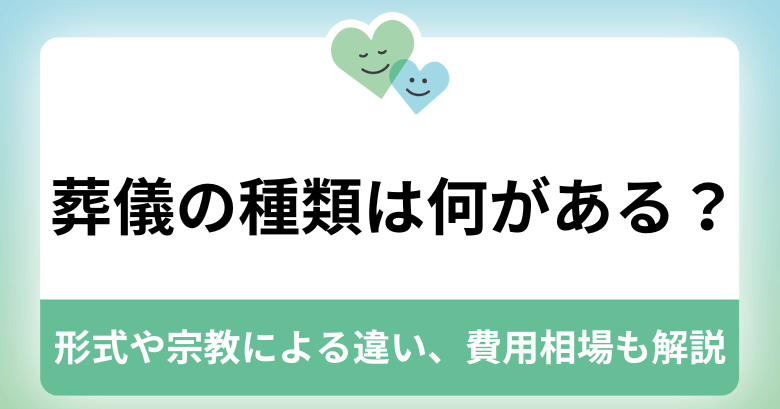※当記事はPRを含みます。
「家族・親族に認知症患者がおり、相続の際にトラブルにならないか不安」認知症と相続に関して、このようにお悩みの方はいませんか?
法律上、認知症患者は法的に効力をもつ行為ができなくなる関係で、相続に関連して様々な問題が生じる可能性があります。
この記事では、相続人が認知症患者の場合、および被相続人が認知症患者の場合に、どのような問題が生じ、どのような解決策があるのか詳しく解説します。この記事を読めば、今どのような対応をすべきなのか理解できますよ。
- 相続人が認知症患者の場合、相続財産を動かせなくなる可能性がある
- 被相続人が認知症患者の場合、遺言等の効力が争われることがある
- 家族・親族に認知症患者がいる場合には直ちに専門家に相談を
相続人が認知症の場合の問題点
まず、相続人が認知症患者である場合の問題点についてみていきましょう。
認知症の相続人は相続放棄ができない
認知症の症状が進行し、意思能力(法律行為の前提となる意思決定をする能力)や行為能力(単独で法律行為を行う能力)が失われている相続人は、単独で相続放棄をできないのが通常です。仮にそのような人が相続放棄の意思表示をしても、無効又は取り消し得るものとなってしまうからです。
また、親族や他の相続人が、認知症患者の相続人を代理して相続放棄をすることも許されません。これは、代理人を選任するためには本人が代理権を授与する必要があるところ、意思能力や行為能力のない認知症患者(本人)には、このような代理権を授与する能力も否定されるからです。
こうした点に焦点を当てると、非常に不便な制度だと思われるかもしれません。しかし、民法ではあえてこのような規定を置くことで、自身の財産を管理することが難しい認知症患者を守っているのです。
認知症の相続人がいると遺産分割協議ができない
同じく意思能力や行為能力がないことを理由として、認知症患者である相続人は遺産分割協議に参加できないこともあり得ます。
そして、全会一致が求められる遺産分割協議に、相続人の一人が決議に参加できない結果として、遺産分割協議そのものを開催できないことになります。
遺言書がない場合や、遺言書に記載のない相続財産がある場合、各相続人は遺産分割協議を経なければ相続財産を受け取れません。
そのため、各相続人は相続財産を自由に処分できず、凍結された預金口座から預金を引き出すことも、不動産を処分することもできなくなってしまいます。
遺産分割協議書を偽造した場合には罪に問われることも
遺産分割協議を成立させるため、認知症患者の相続人の署名を偽造する行為は私文書偽造の罪に問われる可能性がありますし、そのような一部偽造により作成された遺産分割協議書の法的有効性も否定されます。
そのため、遺産分割協議書に勝手に押印したり、署名したりする行為は絶対にやめましょう。
相続人が認知症の場合の対応策
ここまで紹介したように、相続人に認知症患者がいる場合には、相続放棄をさせることも、遺産分割協議をすることもできません。このままでは、相続人全員が遺産を受け取れない事態が生じてしまいます。
このような事態に対応するため、民法には対応策が定められています。以下からは、その対応策の具体的な内容を解説します。
認知症の程度を確認する
認知症と一口に言っても、症例や進行状況は患者によって様々です。そのため、「認知症」との診断を受けたからといって、必ずしも意思能力や行為能力がないと即断されるわけではなく、症状の程度によっては意思能力や行為能力があると評価され、相続放棄や遺産分割協議を進められる場合もあります。
例えば裁判所が医師に向けて作成したガイドラインでは、4段階の症例が例示されており、必要な法的サポートも段階的に記されています。
引用元:裁判所-成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引「鑑定書記載ガイドライン」
a 契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができる後見、補佐又は補助のいずれにも当たらない程度。 b 支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある。例えば、重要な財産行為(不動産、自動車の売買や住宅の増改築、金銭の貸し借り等)について、自分でできるかもしれないが、できないおそれもあるという程度の方は、補助に相当すると考えられる。 c 支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。例えば、日常の買い物程度は単独でできるが、重要な財産行為(不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等)は自分ではできないという程度の方は、補佐に相当すると考えられる。 d 支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。例えば、日常的に必要な買い物も自分ではできないという程度の方は、後見に相当すると考えられる。
単独で法律行為ができないのは、被保佐人と被後見人です。すなわち、このガイドラインではcとdに該当するような症例がみられる場合には、相続放棄や遺産分割協議に関する意思表示をしても絶対的に無効となったり、後日取り消されてしまう可能性があります。
一方、bの症例に該当する場合、すなわち被補助人相当の場合には、単独で法律行為ができるかどうかは、裁判所が補助開始の審判をする際に決定されます。つまり、人によってケースバイケースということです。
このように、認知症の症状にはグラデーションがあり、また、一時的に症例が悪化・改善することもあるため、医学的見地から正確に症状を把握する必要があります。
そのため相続関係の手続きをする際には、並行して医療機関での診察と鑑定を行い、どの程度の判断能力があるのか正確に把握しておきましょう。
成年後見制度を利用する
相続人の認知症症状が悪化しており、正常な判断ができない場合(意思能力が認められない場合)には、成年後見制度を利用しましょう。
相続人が事理弁識能力を欠く常況にある場合には、親族や利害関係人からの申立てにより、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
事理弁識能力とは「自分がこれから何をしようとしているのか」を認識できる能力をいい、6歳前後が一応の目安とされています。例えば買い物をするとき、自らに代金の支払義務が、相手方に商品を引渡す義務が生じることを認識できない場合、事理弁識能力がないと判断されるでしょう。
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
引用:e-gov法令検索-民法7条、同8条
成年後見制度のメリット
成年後見人は、成年被後見人(後見される人)の財産の管理を行い、代理人となる権限をもっています。
そのため相続の場面では、成年後見人が被後見人の代理人となって遺産分割協議に参加でき、相続放棄の手続きを行うことが可能です。
成年後見制度のデメリット
成年後見人は被後見人の利益になるように行動するため、被後見人の利益に反する行為(例えば多額の遺産を放棄する行為)は禁止されており、他の相続人との間で意見が対立するケースもあります。
そのため、実務上は被後見人の親族等が後見人に選任されるケースは少なく、一般的にはその地域で活動している弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。専門家が選任された場合、報酬額として月2万円~5万円ほどの費用が必要です。
例えば、仮に共同相続人お一人が他の共同相続人の後見人となる場合では、相続において後見人と被後見人の利害が対立することになります。このような場合には、裁判所に対して特別代理人選定の審判を申し出る必要があります。
なお、成年後見制度は相続関係のトラブルを回避するためだけに選任されるわけではないため、相続放棄や遺産分割協議が終わった後も、本人の意思能力が失われたままなのであれば、後見人の地位は存続します。
成年後見以外の制度が利用されることもある
医師の鑑定により「事理弁識能力を欠く常況」にまで至っていないが、法律行為を行う能力が不十分であると判断された場合には、より権限の弱い保佐人や補助人といったサポート役が選任されることもあります。
先ほど紹介したように、単独で法律行為ができないのは被保佐人と被後見人であり、被補助人が相続に関する意思表示をできるかどうかは裁判所の判断次第です。
| 補助 | 判断能力が不十分 |
|---|---|
| 補佐 | 判断能力が著しく不十分 |
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 |
認知症患者が相続人になる場合の相続対策
ここまでは、相続の開始時点またはそのあとに(被相続人が亡くなった後)、相続人が認知症となってしまった場合の対応を解説しました。
ここからは、このような場合に備えて被相続人側で取り得る対応について紹介します。
遺言書を作成する
被相続人が遺言書を作成していれば、基本的に遺産は遺産分割協議を経ることなく遺言書のとおり相続されます。
そのため、相続人に認知症患者などがおり、遺産分割協議をスムーズに進められる見通しが立たないような場合には、被相続人において遺産相続の方法を記した遺言書を遺しておくことがトラブル予防となります。
なお、遺言書を作成する場合、共同相続人の最低限の相続分である遺留分を侵害しないよう配慮するべきですが、仮に遺留分を侵害するような遺言書が作成されても、遺言書の効力には影響しません。
この場合、相続開始後に遺留分の侵害を受けている者から、遺留分を侵害している者に対して、遺留分侵害額の請求をすることで当事者間の公平が図られることになります。そのため、遺留分の被侵害者が認知症の相続人である場合には遺留分侵害請求等で手間取る可能性がありますので、遺言書作成の際はその点についても配慮する方が賢明でしょう。
家族信託を利用する
他の選択肢として、家族信託の利用が挙げられます。家族信託は財産管理方法のひとつであり、将来自分が財産を管理できなくなった場合に備え、財産を管理する権限を家族に与えることをいいます。
例えば、父と、認知症患者である母、子が一人いる場合を想定してみます。ここで、父が生前対策をせずに亡くなった場合、相続財産の半分を認知症患者である母が相続し、遺産分割等ができない凍結状態に陥ります。
そこで、生前に父が子に財産を信託しておくと、子が信託された財産については信託契約に基づいて処分・管理をすることとなり、信託の対象となる遺産については遺産分割協議をする必要はありません。
なお、父が子に全財産を信託すると、生前に父は自由に財産を使えなくなるのでは?と疑問に思うかもしれません。このあたりは、信託契約において財産の管理・処分の方法を明記しておけば、特にトラブルになることはありません。
信託契約で父(被相続人)にも受益権を認める場合、信託契約で特別に手当しておかなければこの受益権は父の死亡に伴い遺産分割の対象となり得るので注意が必要です。
被相続人が認知症だった場合の問題点
すでに亡くなった被相続人が認知症患者であった場合、作成していた遺言書の効力が争われる可能性があります。
意思能力がない状態で作成された遺言は無効となるため、遺言作成時に意思能力があったかどうかが相続人の間でトラブルになりえるのです。
もっとも、既に亡くなっている被相続人の、過去の精神状況を正確に把握することは極めて困難であり、相続人同士での話合いでは決着がつかないことがあります。
遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割調停や遺産分割審判だけでなく遺言無効の確認訴訟など、裁判所を解した手続きに移行することとなり、ますますトラブルが泥沼化してしまいます。
親(被相続人)が認知症の疑いがある場合の相続対策
親が認知症患者であり、今後起きるであろう相続に備える方法として、下記の3つの生前対策が挙げられます。
認知症の進行には個人差があり、予測することが困難です。しかし先ほど紹介したように、認知症患者が被相続人となった場合にも相続トラブルに発展する可能性があります。
そのため、認知症患者である親が被相続人になることが予想される場合には、病状の進行が進まないうちに、早めに相続対策を行いましょう。
遺言書を作成する
まず、認知症の進行前、親がまだ意思を明確に伝えられる段階で、親の意思に基づいて遺言書を作成してもらうことをおすすめします。
遺言書は特定の要式により作成する必要があり、これがなければ無効となります。もっとも推奨されるのは公正証書遺言の作成です。公正証書遺言は、公証役場での手続きであり、親の意思がしっかりと確認された上で記録されるため、その内容の確実性が高まります。
認知症の親を持つ家族にとって、特に遺言書は重要なものとなるため、早めの対策により将来の相続問題を回避しましょう。
生前贈与をする
認知症の症状が進行する前であれば、生前贈与をする方法もあります。生前贈与は、将来的な相続トラブルを未然に防ぐだけでなく、資産の有効活用や税負担の軽減にも繋がります。
ただし生前贈与を行う際は、いくつかの点に注意しましょう。まず、贈与税の問題です。年額110万円を超える贈与を行うと贈与税の課税対象となるため、控除内での贈与を行いたい場合には数年に分けて贈与しなければなりません。
認知症の症状が進行すると、生前贈与の意向を確認することが難しくなるばかりか、後になって贈与の意向は無効と判断される可能性もあります。
そのため、十分なコミュニケーションと確認を行いながら、適切な対策を進めることが重要となります。
任意後見制度や家族信託を利用する
親の認知症が進む前であれば、任意後見制度や家族信託制度を利用する選択肢も考えられます。
法定後見制度の場合、後見人が任命されるのは、認知症の状態がかなり進行してからであり、相続対策としてはほとんど機能しません。
一方、任意後見制度を利用すれば、認知症の初期段階から相続や資産管理のサポートを受けることができます。この制度を利用することで、親の意思に沿った適切な資産管理や相続対策を進められます。
また、親が認知症になる前に家族信託契約を結んでおくことで、遺産分割協議や成年後見人の選任手続などの面倒な手続きをすることなく財産を管理できます。
おすすめの記事
ほかにもこちらのメディアでは、法定相続人が放棄した場合についてや相続を弁護士に相談する場合についても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。