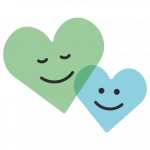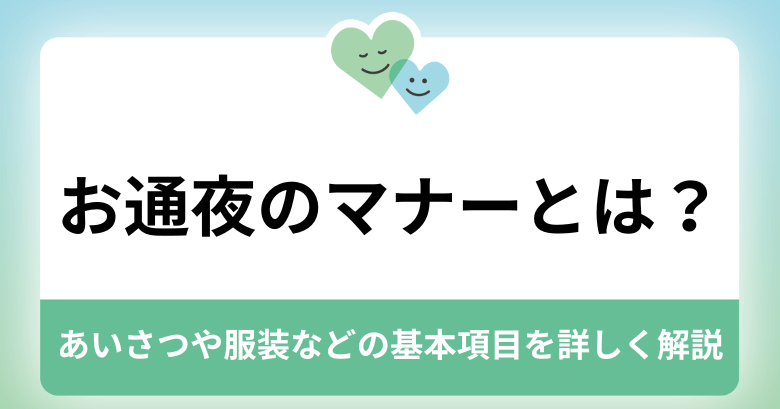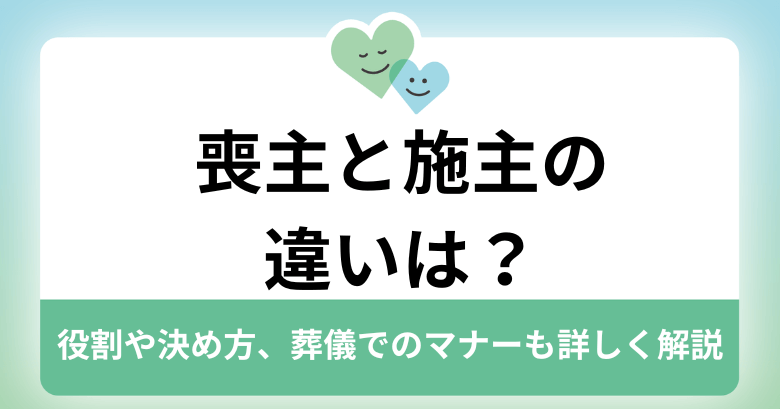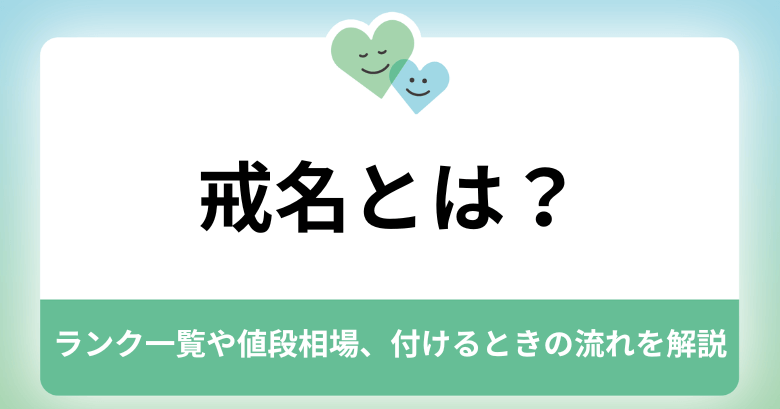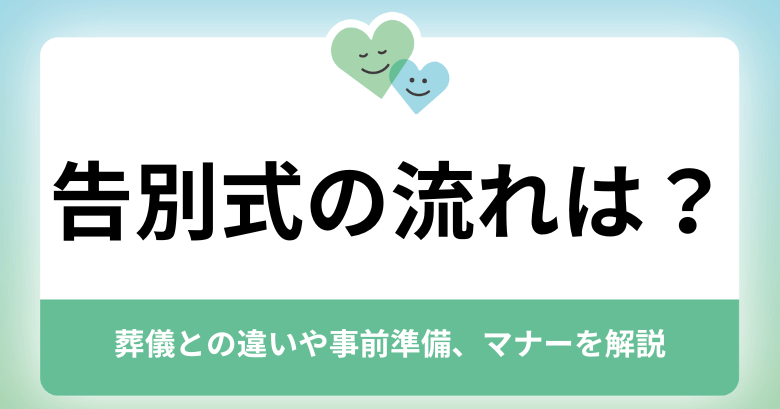
※当記事はPRを含みます。
告別式がどのような流れで進むのかわからず、困っている方も多いのではないでしょうか?
告別式には、受付から出棺までさまざまなマナーがあります。当日の流れと作法を確認しておけば、運営する側も参列者もスムーズに対応できるでしょう。
今回は告別式の一般的な流れを解説するとともに、事前に準備しておくことや参列時のマナーをご紹介します。
- 告別式とは、一般会葬者が参列して故人に別れを告げる社会的な儀式
- 告別式を行う前に、焼香や弔辞・弔電の順番を決めておく
- 告別式では、男女ともに黒を基調とした服装で参列するのがマナー
告別式とは?
告別式とは、故人に最後の別れを告げる儀式です。現在の葬儀は2日間に分けて儀式を行うのが一般的であり、1日目に通夜、2日目に葬儀と告別式を行うケースが多くみられます。
日本で初めて告別式を行ったのは、明治時代の思想家である中江兆民です。それまでの葬儀は、通夜後に葬列を組んで寺院や墓地に向かい、埋葬する流れが一般的でした。
しかし、中江兆民が宗教色を排除した葬儀を強く希望したことから、日本で最初の告別式が生まれたとされています。昭和に入り都市化が進むにつれ、葬列を組む葬儀は廃れていき、告別式が普及しました。
なお近年は、お通夜で弔問を済ませる方が多く、通夜が告別の場となるケースが増えています。
告別式と葬儀の違い
告別式と葬儀は同日に行われることが多いですが、それぞれ異なる意味合いを持ちます。
| 告別式 | 葬儀 | |
|---|---|---|
| 参列者 | ・遺族 ・親族 ・一般会葬者 | ・遺族 ・親族 |
| 役割 | 社会的な儀式 | 宗教的な儀式 |
葬儀は僧侶を呼んで読経を頂く宗教的な儀式ですが、告別式は一般会葬者が参列してお別れをする社会的儀式であり、宗教的な要素はありません。
ただし現代では告別式と葬儀を区別せず、同時に行うケースが増えています。昼間に開かれる告別式には参列しづらいことから、一般会葬者は通夜に参列するケースが一般的になりつつあります。
告別式の時間・スケジュール
告別式は10〜12時の午前中に開始されることが多く、昼前には終わります。
当日の一般的なタイムスケジュールは、以下のとおりです。
| 10:00〜 | 集合・受付 |
|---|---|
| 10:30〜 | 葬儀 |
| 11:30〜 | 告別式 |
| 12:00〜 | 火葬 |
| 14:00〜 | 解散 |
火葬場の予約時間の関係もあるため、当日はタイムスケジュールどおりに進むことが多いでしょう。
葬儀と告別式とあわせて約1〜2時間程度で行われますが、社葬や団体葬などで参列者が多い場合は長時間にわたることもあります。
告別式の流れ
告別式は受付から始まり、出棺で終わります。告別式の一般的な流れについて、順を追ってご紹介します。
受付
受付は、葬儀の開始30分前から始まることが一般的です。受付担当者は受付時刻よりも早い時間に到着して、香典や記帳内容に間違いがないかを確認して準備します。受付が始まる前に、遺族は席に座りましょう。
参列者は受付でお悔やみの言葉を述べ、香典を渡し、芳名帳に住所氏名を記帳します。すでに通夜で香典を渡している方は、受付でその旨を伝えます。香典を持参していなければ、記帳だけで構いません。
会社や友人の代表として香典を預かっているときは、受付で預かっている香典を渡し、ご自身の名前と預けた方の名前を記帳します。預けた方の記帳はせずに、代表者のみ記帳すればよい場合もあるので、現地で確認しましょう。
記帳を済ませたら返礼品を受け取り、式場内の所定の椅子に座って焼香の順番が来るまで待機します。この際、遺族への挨拶や会葬者同士の挨拶は控えましょう。挨拶は式が終わったあとにします。
開式
開式10〜15分前になったら、式場内に着席します。アナウンスなどで参列者全員の着席が求められるので、その指示に従いましょう。
席は親族席と一般席が分かれており、参列者は表記のある一般席に座り、開式を待ちます。表記がない場合には、スタッフの案内に従いましょう。
僧侶の入場と同時に開式し、読経が始まります。遺族や参列者は、黙礼と合掌で僧侶を迎え入れるのがマナーです。
焼香
僧侶による読経の最中に、焼香を行います。焼香とは、香を焚いて故人を拝む一連の行為です。焼香は喪主と遺族から始まり、 故人と縁が深い順に行います。
焼香のやり方は葬式の宗派に関係なく、ご自身の宗派にそったもので構いません。焼香の回数は1~3回ですが、参列者が多いときは1回に統一されることがあります。焼香をしたら喪主や遺族に黙礼をし、席に戻ります。
特に親しい間柄でない場合は、焼香のあとに退席しても問題ありません。
献花
僧侶の退席後、棺に花を納めて故人とお別れする時間が設けられます。遺族から献花を行い、一般参列者も順に故人の棺へ花を入れていきましょう。
この段階が終わると棺の蓋を閉じるため、家族にとって故人と対面できる最後の機会になります。
釘打ち
最後の対面が終われば、棺の蓋を閉じて釘打ちをします。釘打ちとは、死者が三途の川を無事に渡れるように願って釘を打つ儀式です。血縁の濃い順に、棺の頭の部分にある釘を石で2回ずつ軽く打ち込みます。
しかし、家族の心情として心苦しいことから、近年は釘打ちの儀を行うことは少なくなっています。
出棺
釘打ちが終わったら、故人に近しい男性が棺を霊柩車に運びます。霊柩車へ棺を乗せたら、喪主や親族代表が一般参列者に対してお礼の挨拶をし、火葬場へ向けて出棺します。一般参列者は出発前に黙礼・合掌し、故人の冥福を祈りましょう。
火葬以降は遺族と親族のみで行うケースが多いため、一般参列者はこの段階で解散となります。家族からの依頼がない限り、火葬場に行きたいと申し出ることは控えましょう。
告別式の事前準備
告別式を円滑に行うために、事前に準備しておくことを解説します。
受付担当者の決定
告別式では、斎場の入り口に受付を設置するため、受付担当者を決める必要があります。受付を担当する方に決まりはありませんが、故人の遠い親類や会社関係の方、喪主の友人知人や近所の方が務めることが一般的です。
受付の業務には、香典の管理や記帳の案内だけではなく、斎場の案内も含まれます。そのため、トイレや喫煙所の位置などを事前に確認して、参列者をスムーズに誘導できる準備をしておきましょう。
席次・焼香の順番
通夜と告別式で参列者が異なる場合は、席順と焼香順を決めておきます。
式場のレイアウトにもよりますが、告別式の席は祭壇に向かって右側が喪主と遺族・親族、左側は友人や知人、会社関係の方が座るのが一般的です。一般参列者は左右の席の後方になります。
祭壇に近いほど上座になるので、故人との関係を踏まえて順番を考えましょう。
焼香に関しても同様に順番あり、以下のように血縁関係が濃い順番で行うケースが一般的です。
- 喪主
- 遺族
- 親族
- 参列者
ただし、地域や宗派によってマナーは異なるため、事前確認が必要です。遺族だけで決めずに、葬儀社の担当者や地域事情に詳しい方などと相談しながら準備を進めていくとよいでしょう。
弔辞・弔電の読み上げ順番
弔辞と弔電を読む順番は、基本的に故人に近い方や年長者からとなります。故人との関係性などを考慮し、失礼のないようにするために、葬儀社の担当者からアドバイスをもらいましょう。
弔電が多数届いていて時間内にすべて読み切れない場合は、告別式で披露する弔電を選定します。名前や肩書の読み間違いが起こらないように、司会者と読み方を確認することも大切です。
喪主挨拶
喪主は参列者に対して、故人が生前お世話になったことや参列への感謝などの挨拶を述べる立場です。しかし、喪主が高齢で挨拶ができるか不安なときは、別の家族が挨拶します。
誰が挨拶するのか、何を述べるかは、葬儀担当者と相談しながら決めます。葬儀社では挨拶のサンプルを用意していることもあるので、参考にするのもよいでしょう。
火葬場への同行者数・移動手段
火葬場へ同行する人物は遺族や親族が中心ですが、故人と縁の深い方が同行することもあります。人数によって移動手段も変わってくるため、事前に同行者数を決めておきましょう。
火葬場までの移動手段は、葬儀会社が準備したマイクロバスが一般的です。しかし、マイクロバスを所有していない葬儀社もあるため、その際は自家用車やタクシーなどの移動手段を準備する必要があります。
僧侶へのお布施
告別式が終わった段階で僧侶へお布施を渡したい場合は、事前に準備しておきましょう。お布施を渡すタイミングに決まりはないため、すぐに用意できない場合は日を改めて寺院へ持参することも可能です。
お布施の金額は地域や菩提寺との関係性によって異なりますが、15〜50万円が相場です。お布施の金額について迷ったときは、葬儀社に相談しましょう。
告別式でのマナー
告別式に参列するときは、故人や遺族に失礼がないように注意しなければなりません。ここでは、参列者側が告別式で気を付けなければならないマナーを解説します。
服装
告別式に参列する際は、男女ともに黒を基調とした服装を選ぶのがマナーです。
| 服装 | |
|---|---|
| 男性 | ブラックスーツ 白色ワイシャツ 黒色ネクタイ 黒色靴下 黒色の靴 |
| 女性 | 黒のワンピースまたはスーツ 黒色ストッキング 黒色のパンプス |
| 子ども | 学校の制服 【制服がない場合】 ブレザー 白色のシャツ 黒色の靴 |
喪主や遺族よりも格式の高い服装は着用してはいけないので、正喪服である和装は避け、礼服で参列しましょう。男女ともに華美なアクセサリー類は避けて、失礼にあたらないように落ち着いた服装を心がけることが大切です。
子どもは、学校の制服が正式な礼装となります。制服がない場合は、ブレザーや白色のシャツ、黒色やそれに近い地味な色のスカートやズボンを選びましょう。
幼児や乳児は黒色や地味な色の服装を選べば問題ありません。
香典
香典は香典袋に入れて、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのがマナーです。袱紗を忘れたときはハンカチで代用できますが、紫やグレーなどの落ち着いた色を選びましょう。受付で香典を渡すときは、袱紗から香典袋を取り出して渡します。
香典の金額は、亡くなった方との関係性によって異なります。
| 故人との関係 | 香典の金額 |
|---|---|
| 親 | 10万円 |
| 兄弟姉妹 | 5万円 |
| 祖父母 | 1万円 |
| 叔父叔母 | 1万円 |
| 友人・知人・職場関係 | 5,000円 |
血縁関係が近いほど多く包みますが、「死」や「苦」を連想させる4や9の金額は避けるのが一般的です。
また、新札は死を準備していた印象を与えることから、葬儀で使うのは望ましくないとされています。新札しかない場合は、一度折ってから包めば問題ありません。
香典には、結び切りの水引が付いた香典袋を使用しましょう。ただし、金額と見合う香典袋を使用することがマナーなので、5,000円以下の香典を包む場合は、水引が印刷された香典袋で十分です。
表書きは仏式なら「御香典」で問題ありませんが、一般的に「御霊前」が使われています。宗教や宗派がわからないなら「御霊前」で問題ないでしょう。
参列
参列者は、時間に余裕をもって式場に到着しましょう。
通夜なら遅れて参列しても問題ありませんが、告別式は火葬場の予約時間などの都合もあるため、スケジュール調整が困難です。遅れて参列すると最後のお別れができないので注意しましょう。
喪主は段取りの確認などで忙しいため、お悔やみを述べるときも長く時間を取らずに、挨拶程度にとどめておきます。出棺前にお別れするときも、ご自身の順番が済んだら速やかに場所をあけましょう。
参列できないときは、弔電やお悔みの手紙などを送ります。この際、文中に参列できない事情を記載しますが、長く述べる必要はなく、「やむを得ない事情があり」などと簡潔に述べれば十分です。
その他、弔意を伝えるために供花や香典を送る方法もあります。
おすすめの記事
ほかにもこちらのメディアでは、葬式の流れについてや通夜と告別式の違いについても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。